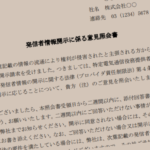名誉毀損の開示請求 拒否する場合の「不同意の理由」書き方を解説

「侵害された権利」の欄に「名誉権」(名誉毀損)と書かれた意見照会を受け取ったときの、拒否(不同意)の理由の書き方について解説しています。
名誉毀損の成立要件
法律上、名誉毀損(民事)が成立するためには、以下の要件が必要です。
① 特定性(同定可能性)がある
② 投稿によって社会的評価が低下した
③ 違法性阻却事由がない
この①~③いずれかが認められない場合には名誉毀損は成立しません。そのため、開示請求を拒否(開示に同意しないと回答)する際は、このいずれかが認められないことを拒否の理由に記載することが有効です。
特定性(同定可能性)に対する反論
名誉毀損が成立するためには、その投稿が「開示請求者のことを指している」といえることが必要です(このことを「特定性(ないし同定可能性)」といいます。)。
そのため、「誰のことを指しているかわからない」あるいは「他の人のことを言っているとも読める」という場合には、特定性が認められず、名誉毀損は成立しないことになります。
書き方はケースによってまちまちですが、記載例としては以下のようなものになります。
- 投稿の対象者について、何も情報(氏名、性別、所属など)が書かれておらず、誰のことを言っているか読み取れない
- 「Wさん」とイニシャルが書かれているだけで、「W」に該当する人は複数いる
- 「経理部の女」と書かれているが、経理部の女性従業員は複数いる
- 「あのデブ」とだけ書かれているが、ふくよかな方は大勢いる
ただし、特定性は前後の文脈も含めて判断されます。
そのため、単にその投稿に書かれたものが「源氏名や伏字、イニシャルだけ」という主張だけでは特定性が否定されるとは限りません。
開示請求者側も、何か根拠があって「自分のことだ」と思っているわけですから、特定性の点で反論する場合は説得的な記載が必要になります。
社会的評価の低下に対する反論
名誉毀損が成立するためには、その投稿によって「社会的評価の低下したこと」が必要です。(社会的評価の低下とは聞きなれない言葉だと思いますが、「世間のイメージ・印象が悪くなる」程度の意味です。)
そして、社会的評価が低下は、(ネガティブな内容の)具体的事実が指摘されたときに発生すると一般的に考えられています。つまり、具体的事実の指摘がない、単なる意見だけでは基本的に社会的評価は低下しないと考えられています。
そのため、社会的評価の低下に対する反論としては、「具体的事実の記載がない(単なる意見である)」という主張が考えられます。
- 「ワンマン社長」と書かれているが、「ワンマン」経営それ自体は悪いことではない
- 「料理がまずい」と書かれているが、単に感想を書いただけで社会的評価が低下するとまではいえない
- 「ムカつく」と書いたが、単に主観を言っただけ
また、投稿記事の記載を不自然に解釈し、具体的事実の指摘があると主張されることがあります。そのような場合は、投稿記事の記載を読んだときの「自然な解釈」を反論として説明するのが効果的です。
開示請求者は、投稿記事のうち「料理が美味しくなかった」という記載について「腐った材料を提供しているという事実の指摘である」と主張しています。しかし、そのような解釈をすることは不自然であるといえます。この記載は、料理を実際に食べた客の「美味しくなかった」という意見を述べたに過ぎないと解釈することが自然です。
違法性阻却事由がある
違法性阻却事由というものがあると、名誉毀損は成立しません。
名誉毀損の場合、次の3つの要件すべてが認められれば違法性阻却事由があると判断されます。
- 表現の内容が公共の利害に関することがらであること
- その表現がもっぱら公益を図る目的でなされたこと
- 摘示された事実が真実であるか、真実と信じたことについて相当の理由があること
このうち、発信者情報開示請求との関係で最も重要なのは③であり、③を説明することで十分なケースが多いといえます。
ただし、③を効果的に説明するためには、証拠の提出を考える必要があります。
開示請求が任意請求の場合は証拠がなくても非開示にできるかもしれませんが、裁判になっている場合は証拠の提出がなければ厳しいといえます。
また、書き方としては、単に「投稿内容は真実である」と書くだけでは弱いでしょう。5W1Hを意識し、時系列で整理すると説得的な文章となります。
さらに、報道などを根拠にしたのであれば、実際の報道内容を指摘することも必要です。
- ○○年○○月○○日○○時ころ、A部長がB係長に対し、○○株式会社の3階の会議室で「お前は能無しだ、クビにしてやる」などと怒鳴りつけていた
- ○○新聞の○○年○○月○○日付のニュース記事で、開示請求者が○○していたことが報道されている
名誉毀損のケースでの拒否理由の書き方の説明は以上のとおりですが、もちろん具体的な記載はケースによって違いますし、実際に文章にするのが難しい場合もあると思います。
意見照会書への回答について相談されたい方は、当事務所にぜひ一度お問い合わせください。
弁護士に依頼できることや費用の目安等についてはこちらをご覧ください。
発信者情報開示請求について、発信者側の解説記事についてはこちらをご覧ください。