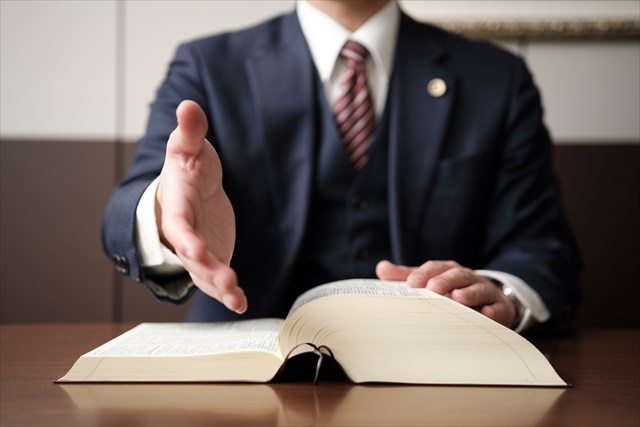ソフトの不正インストール|示談金の額や減額の可能性について解説

ソフトウェアメーカーや、BSA、ACCSなどの団体から不正利用(不正インストール)の通知が届くというケースが多くあります。
そのような通知をきっかけに示談交渉が開始されることも多いですが、最終的に成立する示談がどのようなものになるか、気になる方も多いと思います。
そこでこの記事では、ソフトウェアの不正利用が発覚したケースでの示談金の額はどのようなものか、減額の可能性はあるのかについて解説しています。
この記事はこんな人におすすめ
- ソフトウェアの不正利用(インストール)があると指摘する通知が届いた方
- 不正利用が発覚したケースでの示談金の額の計算方法が知りたい方
- ソフトウェアの不正利用で莫大な示談金の請求を受けている方
>>「ソフトウェアメーカーからの」通知書への対応方法については以下の記事で解説しています。
示談金の計算方法
法律的には、ソフトウェアの不正インストールは著作権侵害であり、民法上の不法行為に該当します。
このときに請求される損害の項目は、以下のものが一般的です。
- 著作権侵害による損害
- 弁護士費用
- 遅延損害金
これらを順番に解説していきたいと思います。
① 著作権侵害による損害
著作権侵害による損害は、基本的には次のように計算されます。
ソフトウェアの小売価格はある程度客観的に決まっているので、示談で最も問題になるのは不正インストールの件数でしょう。
この件数は、こちらが不正インストールを認めた場合はその件数、認めなかった場合は証拠保全や任意調査で確認できた件数になることがほとんどです。(その他、不正インストールの告発をした人の情報から認定するということも考えられますが、告発した人が確たる証拠を提出していない限り、この件数で認定されることはないと思われます。)
>>ソフトウェアの不正利用に関する立入調査や証拠保全についてはこちらの記事で解説しています。
② 弁護士費用
ここでいう弁護士費用は、損害賠償請求にかかった弁護士費用です。
基本的に、裁判で認められるのは、①で認められる金額の10%です。つまり、著作権侵害による損害が100万円であれば弁護士費用は10万円となります。
実際に著作権者が弁護士に支払ったのはこれより多い金額かもしれませんが、ほとんどの裁判例では10%に限り認められていますので、示談の場面でも最終的にはこれに従って計算されることが一般的です。
③ 遅延損害金
遅延損害金は、法的には不正インストールを行ってから実際に損害賠償を支払うまで年3%で計算されます。
例えば、①著作権侵害による損害が100万円の場合、②弁護士費用は10万円になります。そして、不正インストールがあった日から実際に損害賠償を支払うまでがちょうど1年だとすると、遅延損害金は3万3000円になります。
この場合、示談金の額は113万3000円となるということになります。
金銭以外の条件
示談の際は、ソフトウェアメーカー側が示談書を提示することが一般的です。そのような示談書には金銭の支払い以外にも、以下のような条件が記載されています。
著作権者側から提示される示談書は分量がかなり多いこともあります。その文書チェックについては弁護士に依頼することも有用です。
示談金の額を減額することはできるか
不正利用していたソフトウェアが業務用の非常に高価なものである場合や、不正インストールの件数が非常に多い場合などでは、請求される金額が莫大なものになるケースも珍しくありません。
そして、示談金額は上記のとおりある程度機械的に計算されるため、示談金の額を減額することは簡単ではありません。
とはいえ、計算の根拠となった小売価格や不正インストールの件数が著作権者側にとって不当に有利に設定されていることがあります。また、そもそも著作権者側が把握している不正インストールの事実が本当に正確なものかについても争う余地はあります。
その他、長期間の分割払いを認める示談が成立することもあります。
当事務所では、不正インストールの通知が来たケースの対応に豊富な実績があります。
ご心配事やご相談したいことがある場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。