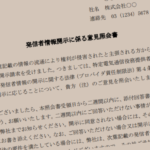まとめサイト運営者に知ってほしい「パクり」の種類や対処法
「WELQ」の事件により、キュレーションサイトやまとめサイトに対する批判が高まっています。
これによってキュレーションサイトやまとめサイトの炎上の危険性は高まっており、第二の「WELQ」が生まれる可能性も十分にあるところです。
そこで今回は、キュレーションサイトやまとめサイトをこれからはじめる方だけでなく、すでに運営している方にもできる法的な対処法について説明してみます。
「パクり」の批判への対処法
キュレーションサイトやまとめサイトへの批判として大きいものは、「他人のコンテンツをパクっている」という点です。
「パクり」は法的には著作権の問題ですので、法的対処法としても、著作権侵害にならないようにすることが重要です。
対処法は、「パクり」(つまり類似の)コンテンツの種類によって変わってきます。
画像の「パクり」について
写真やイラストなどの画像は、ほとんどすべてに著作権が認められます。
そのため、ネット上から適当に拾ってきた画像を利用することは著作権の問題があり、批判の対象となります。
万が一著作権を侵害する形で画像を使用している場合は、画像の差し替えを行いましょう。
また、画像素材を提供するサイトを使用していることもあると思いますが、そこの利用条件に違反していると、著作権侵害になります。
そのため、利用している画像提供サイトの利用条件(利用規約)はもう一度確認しましょう。利用条件に違反していることが判明している場合は、その条件を満たすよう使用形態を変えることや、画像の差し替えの対処が必要です。
※画像の著作権について詳しくはこちら
文章の「パクり」について
文章にも著作権は認められますから、誰かのブログ記事などをコピペすることは著作権侵害の行為として、批判の対象となります。
もっとも、文章の「内容」については、著作権は認められません。つまり「表現」が違えば、「内容」が同じであっても著作権侵害とはならないのです。
小手先の加工(例えば、「~です。~ます。」調を「~だ。~である。」調に変えるだけ)では著作権侵害となりますが、文章の流れや構成まで変えてしまえば、著作権侵害とはなりません。
コピペに近い形で記事を流用しているような場合は、(「内容」が同じでも構いませんので)独自の「表現」といえる程度にまでリライトすることが必要でしょう。
また、「引用」として利用する場合は、その要件を満たすことが必要です。
※「内容」と「表現」について詳しくはこちら
※「引用」について詳しくはこちら
表示・広告規制違反への対処法
今回の「WELQ」事件では、薬事法の表示規制違反が批判の対象となりました。
薬事法をはじめ、法律には「表示すべきもの」「表示してはいけないもの」のルールが多く存在しています。
そのため、コンテンツの内容を確認し、表示・広告規制違反がある場合はすぐに削除またはリライトしましょう。
表示・広告規制がある代表例は、次のとおりです。
・金融商品取引法
・景表法(不当景品類及び不当表示防止法)
・特商法(特定商取引に関する法律)
・消費者保護法 など
どのような表示・広告規制が適用されるかは、サイトの種類によって変わってきます。自身のサイトに表示・広告規制が適用されるものであるかは一度確認してみましょう。
情報の「発信者」としての自覚をもつこと
キュレーションサイトやまとめサイトは、他者の作ったコンテンツを使用するものです。
しかし、そのコンテンツを使用している以上、サイト管理者自身にもそれらのコンテンツの内容について責任があります。
”自分が作ったものでないから関係ない”ということはできません。
「WELQ」の問題も、外部ライターや一般ユーザーに記事作成を任せ、内容のチェックがずさんになっていたことが炎上の原因のひとつでした。
キュレーションサイトやまとめサイトを運営するときも、やはり情報の「発信者」としての自覚をもつことが、炎上を防止する最も重要な心構えといえます。
「WEBに関わる法律講座」の運営元である四谷コモンズ法律事務所では、投稿型サイト等の管理者向けのサービスを提供しております。問題が大きくなる前に、ぜひ本サービスをご利用ください。
[button style=”btn-default btn-sm” type=”link” target=”false” title=”サービスについて詳しく知る” link=”https://y-commons.com/service-kanri/” linkrel=””]
警察から捜査関係事項照会がきたときの回答|強制力はある?
電子掲示板やSNSなどの投稿型サイト(CGM)を運営していると、警察などの捜査機関から発信者情報開示(IPアドレスなど)の要請が「捜査関係事項照会書」の形でなされることがあります。
警察からの要請ということで、漫然と応じている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、警察からの要請だからといって、それが免罪符になるわけではありません。
情報開示後の発信者からの権利主張(プライバシー権侵害)に対して、「警察からの要請だから応じた」ということを反論として使うことはできないのです。
もちろん、警察が守ってくれるわけでもありません。
そこで今回は、警察から捜査関係事項照会がなされたとき、サイト側が回答する際の考え方について説明したいと思います。
捜査関係事項照会には”強制力”はない
まず認識しなければならないのはこの点です。
警察からの要請を拒否すると、「公務執行妨害」などとして逮捕されるのではないかと考える方もいると思います。
しかし、そんなことはありません。
捜査関係事項照会などはあくまで任意の手続であって、強制力はないのです。
そのため、回答を拒否したからといって、このことを直接の理由として逮捕がなされることはありません。
”サイト側が犯罪を助長している”とみられることが最大のリスク
とはいえ、回答に応じないことにサイト管理者の逮捕リスクが全くないわけではありません。
犯罪を直接行っていない場合でも、犯罪を助長・促進している場合には、「幇助」として刑事処分の対象になることがあります。
つまり、サイト管理者が適切に捜査に協力しないことでサイト上で行われている犯罪を助長・促進しているとみられるような場合には、サイト管理者も「幇助犯」として逮捕されることがあります。
リスクが高い類型は例えば次のようなケースです。(あくまで一例です。)
これらの場合は、捜査に協力し、サイト上で犯罪行為がなされることを防止すべきでしょう。
・拳銃や日本刀などの取引にサイトが使用されいている場合
・覚せい剤など違法薬物のやりとりにサイトが使用されている場合
・児童ポルノが投稿されたり取引されているような場合
・テロ、殺害などの犯罪予告が行われている場合
・ストーカー行為に使用されている場合 など
なお、警察から記事の削除要請がなされることがありますが、上記のようなケースでは削除に応じるべきと考えます。
捜査の対象にならないものには注意
警察などの捜査機関は、あくまで刑事処分の対象となる行為について捜査の権限があります。
そのため、例えばプライバシー権侵害や肖像権侵害など刑事処分の対象とならないものに関しては、サイト管理者も逮捕リスクなどを考える余地はありません。
微妙なものは、名誉毀損や業務妨害のケースでしょうか。
これらは刑事処分の対象となるものではあります。
しかし、ネガティブな内容も正当な表現の範囲内とされるケースは多いものです。
そのため、例えば企業の批判や商品のレビューなどについては、表現方法や内容なども考慮し、慎重に検討しましょう。
いかがでしたでしょうか。
私個人としても、犯罪捜査に協力することは基本的には善い行いだと思いますし、”捜査にはなるべく協力すべきでない”とは考えてはいません。
しかし、警察からの要請に漫然と応じることには法的リスクがあるということは認識しておくべきだと思います。(また、簡単に削除や情報開示に応じると今度はユーザーが離れてしまいます。そうなるとサービスとして成立しないことになります。)
とはいえ、警察対応や逮捕リスクはデリケートな問題もあります。
捜査関係事項照会の回答にお困りの場合は、一度専門家に相談されることをお勧めします。
「WEBに関わる法律講座」の運営元である四谷コモンズ法律事務所では、投稿型サイト等の管理者向けのサービスを提供しております。問題が大きくなる前に、ぜひ本サービスをご利用ください。
[button style=”btn-default btn-sm” type=”link” target=”false” title=”サービスについて詳しく知る” link=”https://y-commons.com/service-kanri/” linkrel=””]
ピコハラってハラスメント?PPAPの著作権や商標について解説
ピコ太郎さんの「PPAP(ペンパイナッポーアッポーペン)」が人気を集めていますね。
忘年会でPPAPを強要されることが「ピコハラ」(”ピコ太郎ハラスメント”の略でしょうか)だという指摘もあるみたいです。
たまには楽しい記事も書きたいので、今回はPPAPを弁護士が法律面から(真面目に)考察してみたいと思います。
PPAPの著作権
PPAPは、音楽、歌詞、振付けから構成される作品です。それぞれについて著作権が認められるかを検討してみましょう。
(1) 音楽
音楽には当然著作権が認められるもので、PPAPも例外ではありません。
JASRACへの管理信託もすでにされているようですね。
(2) 歌詞
歌詞は正直微妙だと思います。
使われている単語や文章は非常に単純ですから「ありふれた表現」とされる可能性は高く、著作権が認められる範囲は狭いような気がします。
現実的にも、「I have a pen.」と言ったらピコ太郎さんに対する権利侵害だ、なんて言われたらたまりません。
歌詞について著作権侵害が認められるとすれば、歌詞の全部又は大部分をまるまるコピーしたような場合でしょうか。
なお、歌詞についてもJASRACに信託されているようです。(もっとも、このことと、歌詞にどの程度著作権が認められるかは別の問題です。)
(3) 振付け
振付けに著作権が認められるかも、ちょっと微妙です。
ダンスの振付けについて、既存のステップを組み合わせたりアレンジを加える程度では著作権は認められないと判断されたことがあるからです。(社交ダンスの振付けの著作権が問題となった事例ですが)
振付けに著作権が認められるためには、「顕著な特徴」が必要とされていますが、PPAPに「顕著な特徴」はあるでしょうか。果物にペンを指す動作は特徴的といえますが、ここに著作権を認めるに足りる「顕著な特徴」があるといえるかは・・私には判断できません。
なお、同じく流行になっている「恋ダンス」の振付けには著作権が認められそうな気がします。
PPAPの商標
特許情報プラットフォームによれば、「PPAP」のほか、「APPLE PEN」や「PINEAPPLE PEN」などが商標出願されているようです。
本記事作成の時点ではまだ出願中で登録はされていないようですが、登録が完了すれば「PPAP」を商品名やサービス名として使うと商標権侵害となるケースが出てきますね。
PPAPを忘年会で踊ってもいい?
PPAPの音楽には少なくとも著作権が認められるでしょうから、忘年会で踊ってもいいかは一応気になりますね。
結論からいえば、非営利目的・無料・無報酬であれば、踊っても構いません。
忘年会の一発芸であれば営利目的はないでしょうから、一発芸のためにピコ太郎さんに許可を求めるまでの必要はないでしょう。
(なお、「踊ってみた」の動画をYOUTUBEなどにアップロードする行為は著作隣接権も関係する議論ですのでここでは割愛します)
「ピコハラ」は違法? 犯罪行為?
PPAPを踊らせることがハラスメントとして損害賠償の対象となるでしょうか。
多分程度によりますが、損害賠償の対象となるケースはあまりないと思います。
ハラスメント行為について損害賠償が認められるのは、それによって人格的な利益が害されたといえるためです。
PPAPを踊らせることは人格を傷つけること、とまではいい難いように思います。(そこまでいったらピコ太郎さんにも失礼な気がします)
もっとも、再三拒否したにもかかわらずムリヤリやらせるとか、踊らなかったことを理由に解雇や懲戒などを行うようなケースでは違法と判断されるでしょう。
また、暴行や脅迫を用いてPPAPを踊らせるときは、強要罪が成立することがあります。
まだまだ法的検討の余地はありそうですが、キリがないのでこの辺で終わりにします。
年末にかけて、踊る人もそれを見る人も増加すると思いますが、マナーを守って楽しい年末をお過ごしください。
弁護士への法律相談(初回30分無料)はこちらから。
サイト上での画像の盗用・・・ 対策法は?
ネット上での画像の盗用はかなり前から問題となっていました。
しかし近年でもキュレーションメディアやまとめサイトなどの広がりに伴い、深刻な問題として再認識されているようです。
最近でもこんなニュースがありました。
まとめサイトの盗用、ある“浴衣画像”が「収拾つかない」事態に
(2016年12月7日 株式会社朝日新聞社「withnews」HPより)
そこで今回は、そんな”古くて新しい”画像盗用の問題と(法的な)対策法について説明してみます。
画像の盗用は、当然に”著作権侵害”
ネット上の画像をコピーし、他のサーバーにアップロードしてサイト上で公開することは著作権侵害となります。
著作権法においては、「著作権の保護を受けるものかどうか」という議論がありますが、画像の盗用に関してはこれを考える必要ないでしょう。画像は文章などに比べ、”著作権の保護を受ける”と判断されるハードルは低いからです。
”よく似た別の画像を作っている”とか、”うちのサイトにある画像を参考にされた”とかのケースであれば話は別ですが、丸パクリや一部トリミングして使用されたなど(いわゆる「盗用」)のケースでは、ほとんどの場合で著作権侵害があるといえるでしょう。
画像が盗用されたときにできること
画像が盗用された、つまり著作権が侵害された場合は、加害者に対して差止(削除)請求と損害賠償請求ができます。
差止(削除)請求は、その画像を掲載しているサーバの管理者に対しても行うことができます。
なお、加害者が誰か分からないときでも、発信者情報開示の制度を使うことで、加害者を特定できる場合があります。
著作権を持っていることの証明方法は?
差止(削除)のケースでも損害賠償のケースでも、自身が著作権を持っていることを証明しなければならないことがあります。
これについては、元データを持っていることを示すなどの必要がありますが、これでは誰の目からも”著作権を持っている”ことが明らかとはいえませんから、場合によっては無意味な争いが生じる可能性もあります。
この点をクリアするもっとも簡単な方法は、画像に「著作権表示」をして公開することです。こうすることで、”著作権を持っている”ことが明確になりますし、法律上も権利を持っていると推定されることになります(14条)。
著作権表示の方式は「作者名として通常の方法により表示」されていればよく、それ以外の制限はありません。
そのため「Photo by ●●」とか「© ●●」などといった表示で問題ありません。
損害賠償を効果的に行う方法は?
著作権侵害の被害者は、加害者に対して損害賠償請求ができます。
ただ、何も対策をしていなければ、賠償額は微々たるものになったり、ときには全く賠償金が取れないというケースもあります。
これを防止するための最も良い方法は、画像の使用料をサイト上に明示しておくことです。
画像販売サイトでなくとも、例えば「当サイトに掲載された画像の使用量は、一律●●円です」などと表示することは可能です。
このように表示しておくと、盗用された際の損害賠償額についてこの金額を基準とすることができます。
なお、あまりに多額の金額を表示しておくと無効となる可能性もありますので、画像販売サイトの価格なども参考にしながら、妥当と思われる金額を表示しておきましょう。
画像盗用の問題は極めて深刻ですが、事前に対策しておくことで、法的にかなり有利な状況を作れますし、それが強い抑止力にもなります。
ただ、実際に加害者に請求するなどの場合は法的な手続が必要な場合もありますから、盗用でお困りの際は一度専門家に相談されることをお勧めします。
弁護士への法律相談(初回30分無料)はこちらから。
運営者視点からみる「WELQ」炎上事件とキュレーションサイトの法的リスク
株式会社ディー・エヌ・エーの運営するサイト「WELQ」が”炎上”し、全記事の非公開に至ったという報道が話題となっています。
(平成28年11月29日 株式会社ディー・エヌ・エーHPより)
すでに多くのメディアが問題の分析や指摘を行っておりますので、本記事では、サイト運営者の視点から今回の事件の分析をしてみたいと思います。
キュレーションサイト側の狙い
キュレーションサイトに限らず、ウェブ上のメディアは独自の記事をより多く持つことをひとつの目標としています。
そうすることでSEO対策につながり、アクセス数が稼げるからです。
アクセス数が稼げることがメディアサイトの正義であり、それを強く推し進めたのが今回の事件の要因のひとつとなっています。
”独自の記事をより多く持つ”ための手段として、DeNAは外注のライターや一般ユーザーに記事作成を行わせていましたが、この手段にある法的リスクが今回の事件を引き起こしたといえます。
どのような点を法的リスクとして認識すべきだったか
「WELQ」のようなサイトを運営するにあたっては、次のような法的リスクを認識すべきといえます。
(1) 外部ライターや一般ユーザーの作った記事でも、サイト側が責任を負う場合がある
「”炎上”のきっかけとなった記事は外部ライターや一般ユーザーが作成したもので、サイト側に責任はない」とすることはできません。
確かに、記事を作成した人の責任もあるかもしれません。
しかし、そのこととサイト側が責任を負うかどうかは別問題です。
特に、サイト側はシステムを管理していますし、作成された記事によって利益を得ています。これらの事情からすれば、記事の内容についてサイト側が責任を負わないと法的に判断されることはないでしょう。
そのため、外部ライターや一般ユーザーが他の記事をコピペするなどして著作権侵害をしたり、法令違反の記事を掲載した責任は、サイト側に降りかかってくることもあるのです。
(2) 契約によっても法的リスクを記事作成者に転化することはできない
外部ライターや一般ユーザーに記事を作成してもらうにあたって、何らかの契約(主に記事の著作権に関して)を結ぶことが通常です。
しかし、この契約だけでは法的リスクを排除しきれません。
なぜなら、契約とは契約当事者だけを拘束するもので、第三者は無関係だからです。
そのため、記事が国の規則に違反していたとか、記事によって第三者に損害が発生したというケースでは、サイト側は記事作成者との契約を盾にして戦うことはできません。
場合によっては、「作成した記事によってサイト側に損害が生じたときは、記事作成者はその損害を補填する義務を負う」などという契約条項が盛り込まれることもあります。
このような条項によって、(有効性が認められた場合に限られますが)ある程度損害を記事作成者に転化させることは考えられます。
しかし、それでもひとたび”炎上”したときのサイト側のレピュテーション低下は避けることはできません。
(3) 利用規約だけでは、法的リスクを排除しきれない
「WELQ」の利用規約には、次のような条項があったようです。
「当社は、本サービスの内容、ならびに利用者が本サービスを通じて入手したコンテンツ及び情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる責任も負わないものとします。」
これにより、記事の内容に誤りがあったとしても、サイト側は閲覧者に対して責任を負わないと読めます。
しかし、このような規定も万全ではありません。なぜなら、事業者の責任を一切免除するような条項は、消費者契約法により無効となるからです。
もっとも、これを見越してか、「WELQ」の利用規約には次のような条項もありました。
「本注意事項において当社の責任について規定していない場合で、当社の責めに帰すべき事由により利用者に損害が生じた場合、当社は、1万円を上限として賠償するものとします。また、当社は、当社の故意または重大な過失により利用者に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。」
消費者保護法によって認められる軽過失の一部免責を規定するものです。ただ、上限が1万円となっており、この額が「消費者の利益を一方的に害する」と判断されれば、やはり消費者保護法により無効となります。
さらに、利用規約はサイト側とユーザーの法的関係のみを縛るものです。国の規制などは別問題ですから、どんなに利用規約を工夫したとしても国の規制を免れることはできません。
法的リスクを効果的に排除するには??
配信の前にしっかり内容をチェックするなど、記事の配信に関して責任ある監督をすべきことに尽きます。
今回の事件により、「記事作成者とサイト管理者が一致しないケースでも、サイト管理者も記事の内容について責任を負うことがある」ということがより明確になりました。
”とにかく記事の量を確保し、問題点を指摘されたときに後から修正すればいい”という考え方は極めてリスクの高いものいえます。
キュレーションメディアは、流行の裏で法的リスクも多く指摘されているものです。運営する際はしっかり法的リスクを認識し、それをできる限り排除する体制の構築が必要でしょう。
弁護士への法律相談(初回30分無料)はこちらから。
【関連記事】
”自炊”で逮捕? 自炊代行の問題点
いわゆる”自炊”を代行する業者が逮捕されたという報道がなされました。
古書店へ転売も、書籍の「自炊代行業」男性を逮捕
(平成28年11月30日 一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)HPより)
差止や損害賠償などを求める「民事」の事件はこれまで何度か報道されましたが、逮捕など「刑事」の事件が報道されたのは今回が初のようです。
自炊で逮捕に至るのか、疑問に思われるか方や不安をおぼえる方もいらっしゃると思いますので、今回は”自炊”の問題点についてまとめてみます。
そもそも”自炊”とは??
”自炊”とは、本や雑誌などをスキャナなどを使ってデジタルデータにする行為です。
タブレット端末などの普及により、本や雑誌をデジタルデータとして閲覧することがますます便利となりました。
また、デジタルデータは場所をとらないのでスペースの節約ができ、劣化もしません。
このような理由から、手持ちの本や雑誌をデジタルデータ化する行為、つまり”自炊”は一般的なものとなっています。
ただ、”自炊”の作業は楽ではありません。一般的な”自炊”の方法は、背表紙を裁断するなどしてページをばらばらにし、それをスキャナに流すというものです。
一冊だけでもそれなりの労力を使うものですから、これを膨大な量の本や雑誌について行おうとすると、かなりの手間と時間がかかってしまいます。
そこで登場したのが”自炊”の作業を本人に代わって行うとする業者で、これが「自炊代行業」とよばれるものです。
”自炊”は違法??
「私的使用のための複製」(著作権法30条)にあたる限り、”自炊”は違法ではありません。
ポイントは、
① 私的使用目的で行うこと
② 使用する者が自分で行うこと
この2点です。
つまり、自分で楽しむために自分で”自炊”の作業を行う限り、違法ではありません。
一方、自炊代行業は、このうちの②が欠けますので、違法と判断されます。(2016年に最高裁で確定しました。)
ただ、自炊代行業も一定のニーズがあるところで、これを違法と判断することは時代に合わないなどといった批判も根強く、”自炊”についての議論が終わったわけではないようです。
今回のケースは何が問題だった??
報道によれば、今回逮捕された自炊代行業のケースは、”自炊”によって得られたデータを他人に転売などしていたという点が特徴です。
つまり、②が欠けるばかりか、そもそも①すら欠けていたというケースです。
自炊代行業肯定論の根拠となっているのは、”業者は顧客の作業を手伝っているだけ” つまり ”業者側は得られたデータは使用せず、データはあくまで顧客が私的使用をするためだけのものである” というものでした。
今回のケースは、業者側もデータを販売するなどしていますから、そもそも私的使用目的ですらなく、どのような考え方によっても違法となる悪質なものでした。
安心して”自炊”を行うためには?
やはり自分自身で”自炊”の作業を行うのが無難でしょう。
(”自炊”の目的で裁断機やスキャナを貸し借りする行為は適法です。)
近しい人に手伝ってもらって一緒に作業を行う程度であれば許され得るでしょうが、自炊代行業を利用する際はやはり著作権に留意しなければいけません。
他人の著作物を無断で複製して販売するなどの行為は犯罪ですから、注意しなければ思わぬところで犯罪に巻き込まれることもあります。
著作権違反の責任は決して軽いものではありません。”自炊”を行う際は、ルールやマナーを正しく守って行いましょう。
弁護士への法律相談(初回30分無料)はこちらから。
【発信者側】開示請求訴訟で請求棄却に成功しました その2
私が発信者側で担当した発信者情報開示請求訴訟で、勝訴(請求棄却)判決を得ることができましたので、お知らせいたします。
※ 前回紹介したものとは別件です。
請求棄却判決が得られたのは、どのような事件だった?
詳細はお伝えできませんが、前回と同様、ある企業に関する投稿が開示対象として争われた事件です。
企業には公的な要素もあるといえますので、企業に関する投稿については、「正当な言論」と判断されるケースが少なくない印象です。
裁判にはどのような形で関わった?
前回と同様、「開示に同意しない(拒否する)」と回答するとともに、「発信者の投稿は違法ではなく、開示の対象にならない」という内容の意見書を裁判所に提出しました。
また、併せて証拠も提出しております。
勝訴の決め手は?
「投稿内容が真実であること」を示す証拠が多くあったことと考えています。
名誉毀損を理由としてなされる発信者情報開示請求訴訟では、「投稿内容が真実であるかどうか」が最も重要な事項のひとつです。
もちろん証拠がなくても戦う余地は十分ありますが、証拠がある方がより効果的に反論できることは確かです。
今回裁判所に提出した証拠はメールやLINEのキャプチャ画像なども含まれました。このようなものでも証拠として高い価値があることが多くあります。
手持ちの証拠が価値の低いようにみられるものであっても、理論の組み立て方や見る角度によっては有効な証拠になることもよくありますから、ささいな反論材料しかないと考えて諦めることは非常にもったいないことです。
不利に思える状況であっても、やはり一度は弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に依頼できることや費用の目安等についてはこちらをご覧ください。
発信者情報開示請求について、発信者側の解説記事についてはこちらをご覧ください。
【サイト・サーバ側】投稿型サイトの管理者が負う法的責任とは?
インターネット上の誹謗中傷やプライバシー侵害が話題になるとき、しばしば取り上げられるのが”サイト管理者の責任”です。
例えば、他人を誹謗中傷するような情報が電子掲示板に投稿されたとき、責任を負うべき人はその投稿をしたユーザーです。
しかし、このような場合、情報を掲載していた掲示板の管理者には、全く責任はないのでしょうか。
今回は、他人の権利を侵害するような情報が投稿されたとき、サイト管理者が負うべき法的責任について解説してみます。
そもそも、サイト管理者が責任を負うことはある?
”他人の権利を侵害するような情報を投稿したのはユーザーであって、サイト管理者は無関係”と考えている方も、中にはいらっしゃると思います。
しかし、過去の裁判例には、サイト管理者に数百万円の損害賠償を認めたものがあります。
このケースは、投稿された情報が名誉毀損にあたるものでした。しかし、プライバシー権侵害や著作権侵害のケースであっても同じように考えられます。
ユーザーから投稿を受け付けるようなサイトの管理者は、口コミサイトであれ動画サイトであれ、投稿されたコンテンツについて責任を負うことがあるのです。
投稿型サイトの管理者が負う3つの責任
投稿型サイトの管理者は、大きく分けて次の3つの責任を負うことがあります。
(1) 削除義務
投稿された情報が他人の権利を侵害するものである場合、サイト管理者は、そのような情報を”削除する義務”を負うことがあります。
サイト管理者がこの削除義務を負うケースは、被害を受けた人に「差止請求」が認められる場面です。
例えば、著作権侵害や商標権侵害がなされたとき、被害者に「差止請求」が認められることは法律に明記されています。
また、法律に明記されているものでなくとも、「差止請求」が認められることがあります。名誉権やプライバシー権などの「人格権」が侵害されるケースが典型です。
名誉毀損やプライバシー侵害を理由とした削除請求は多くなされていますが、これらは、実は解釈によって認められるものなのです。法律に明記されていくとも”削除義務”が認められることがあるために、サイト管理者が対応に苦慮することがあり、また削除が妥当かどうかの議論もしばしば生じるのです。
(2) 発信者情報開示義務
匿名で投稿がなされた場合、被害を受けた人は発信者が誰か分かりません。
そこで、発信者を特定するために、サイト側に発信者に関する情報の開示を求めることがあります。
この開示請求は、いわゆるプロバイダ責任制限法に定められているもので、この法律の要件を満たす場合には、サイト管理者に発信者の情報(IPアドレスなど)を開示する義務が認められることになります。
(3) 損害賠償義務
サイト管理者は、情報の掲載によって被害を受けた人に対して直接損害賠償義務が認められることがあります。
例えば先ほど述べた裁判例では、サイト側が削除義務を怠ったために、損害賠償義務があると判断されています。
もちろん、人の権利を侵害するような情報が投稿されたからといって、直ちにサイト管理者が損害賠償責任を負うわけではありません。
しかし、だからといって”サイト管理者は法的責任を負うことはない”と考えることは決してできませんので、注意しましょう。
このように、投稿型サイトの管理者もさまざまな法的責任を負うことがあります。(なお、上に挙げたものは民事的な責任ですが、場合によっては逮捕などの刑事処分を受けることもあります。)
投稿型サイトは、板挟み
”サイト管理者の責任”を考えるとき、ひとつ注意すべき点があります。情報を投稿したユーザーが常に”悪者”というわけではないということです。
インターネット上に情報を投稿することによって、自身を表現したり、社会にメッセージを訴えるユーザーも多くいます。
そのような投稿に関して、他人に対するネガティブな内容を含むからといって、安易に削除したり情報開示したりしてしまうと、今度は投稿したユーザーの正当な利益を害することになります。
場合によっては、「表現の自由の侵害」や「プライバシー侵害」などとして、投稿者から損害賠償請求を受けることもあり得るのです。
つまり、投稿型サイトの管理者は、情報を投稿するユーザーと、その情報に触れるユーザーの”板挟み”の状態にあるといえます。
投稿型サイトの適切な運営とは
削除請求や開示請求がなされたとき、法的に見て適切な対応がなされているかがポイントです。
投稿型サイトの管理者は、ユーザーによって投稿されたものすべてを監視するまでの法的義務はないとされています。
しかし、そうであるからこそ、削除請求や開示請求には適切に応じることが求められるのです。
”サイト管理者の責任”を考えるときは、違う立場のユーザーの板挟みにあるという状況を理解し、どちらのユーザーにも偏らないバランスを考えることが重要な視点といえるでしょう。
「WEBに関わる法律講座」の運営元である四谷コモンズ法律事務所では、投稿型サイト等の管理者向けのサービスを提供しております。問題が大きくなる前に、ぜひ本サービスをご利用ください。
[button style=”btn-default btn-sm” type=”link” target=”false” title=”サービスについて詳しく知る” link=”https://y-commons.com/service-kanri/” linkrel=””]
【関連記事】
第一回:【サイト・サーバ側】サイト管理者・サーバー管理者が負う責任
第二回:【サイト・サーバ側】削除・開示請求に備えた事前準備
第三回:【サイト・サーバ側】任意請求で削除・開示請求を受けたら?
第四回:【サイト・サーバ側】削除・開示請求には応じるべき?
【写真・カメラと著作権】デジタル時代の写真と法律の基本
写真には、さまざまな法律問題が関係します。
そして近年では、プロの写真家の方や、カメラを趣味にされている方に限らず、ほとんどの人が写真の法律問題を意識する必要があるといえます。
なぜなら、最近ではほぼすべての携帯電話・スマートフォンにカメラ機能が付いているからです。
そこで、デジタル時代の写真と法律の関係について、分かりやすく解説してみたいと思います。
ほとんどすべての写真に著作権が認められる
人が写真を撮ったとき、その写真には著作権が認められることがあります。
そして、写真に著作権が認められるハードルはかなり低く、ほとんどすべての写真に著作権が認められると考えられています。
プロの撮影した写真には目を見張るものがありますが、その域にまで達していなくても、著作権は認められます。
過去の裁判例で、単なる家族写真(奥さんが夫と子を撮ったもの)にも著作権を認めたものがありました。
そのため、”あまり上手に撮れたものでないから、著作権などないだろう”と考えることは誤りです。
”人がカメラを構えてシャッターを押した写真”であれば、著作権が認められると考えましょう。
(以前、サルがシャッターを押した写真の著作権が問題となりましたが、こちらは著作権が認められないことになりました。)
著作権侵害になる範囲は広くない
多くの写真に著作権が認められるとしても、著作権侵害になる利用形態は限られています。
著作権侵害になる典型例は、その写真をコピーしたとか、一部をトリミングをして使ったような場合です。
逆にいえば、そのような利用形態でない限り、著作権侵害になる場面は少ないです。
例えば、撮影場所が同じとか、構図が似ているとか、そのようなケースでは著作権侵害にはならないことが多いでしょう。
人が写り込んでいるときは”肖像権”に注意する
街角などのスナップ写真は、その場所その時代の人々の生活を表すものとして、写真作品の一分野を構成するものです。
しかし、人を写すものは、肖像権の問題を避けて通ることはできません。
肖像権とは、簡単にいえば”自身の姿かたちを撮影されたり、それを公開されたりしない権利”をいいます。
近年ではSNSで簡単に写真を公開できるようになりましたから、最近では特に肖像権の意識の高まっています。
そのため、人の写る写真を撮影・公開するときは、肖像権を意識することが必要です。
スナップ写真の文化は、時代の流れによって変わってきているといえますので、現代の権利意識や価値観に沿うことが求められているといえるでしょう。
その他さまざまな法律問題も
例えば、撮影禁止の場所で撮影することは、民法上の不法行為になり得るほか、刑法上の建造物等侵入罪などに該当してしまうこともあります。
また、いわゆる盗撮などの行為は迷惑防止条例に違反し、刑事処分の対象にもなります。
その他、撮影場所占拠や鉄道の往来妨害など、マナーの問題にとどまらないケースも増えてきています。
法律問題に発展すると、損害賠償や逮捕・起訴などの問題になりますから、ルールは十分に守る必要があります。
いかがでしたでしょうか。
写真と人々の関わり方が大きく変化している時代ですから、写真の撮影・公開、利用には法律への意識が不可欠です。
特に注意すべき場面は次のとおりです。
・ 無断で写真を使用された
・ 他人が写っている写真を撮影・公開しようと考えている
・ 特殊な場所での撮影を考えている
・ 他人が撮影した写真を利用したい
・ 自分の写真が権利を侵害しているとして、法的な請求をされた
これらの場合は、重大な法的問題に発展する場合もありますので、判断に迷われた場合は専門家に相談しましょう。
弁護士への法律相談(初回30分無料)はこちらから。
【ネットショップ側】クーリングオフしたいと言われたら?
運営しているネットショップで、商品がひとつ売れたので商品を発送したが、数日後、お客さんから「思っていたのと違うから、返品したい。」「クーリングオフできるはずだ。」と言われることがあります。
この記事では、このようなケースでどのように対応したらよいか、解説しています。
1.返品したい理由を確認する
商品を発送しているわけですから、売買契約は成立していると考えられます。
売買契約の成立後は、返品が認められるケースは限られます。
返品が認められる典型的な例は、商品に欠陥があるというケースです
今回のケースは、「思っていたのと違う」という理由ですから、検討すべきは「法定返品権」が認められるかどうかでしょう。
2.「法定返品権」が認められる場合かどうかを検討する
厳密には、ネットショッピングのような通信販売において、「クーリングオフ」という制度はありません。
もっとも、似たような制度はあります。それが、「法定返品権」というものです。
「法定返品権」が認められるときは、理由を問わず契約をキャンセルすることができます。
「法定返品権」が認められるのは、次の場合です。
商品が到着した日から8日を経過するまでの間に、キャンセルの連絡がネットショップ側に届いたとき
お客さんのところに商品が到着した日が基準となりますから、配達の追跡サービスなどで到着した日にちの確認は必須です。
3.「返品不可」の記載に効果があるか
ネットショップのサイト上に、「返品不可」と記載があれば、この法定返品権を認めないとすることができます。
しかし、これには細かい条件があり、サイト上のどこかに1つだけ「返品不可」と記載があるだけでは、法定返品権を認めないとする効果はありません。
4.返品にかかる費用は、負担しなくてよい
仮に法定返品権が認められるとしても、返品する際に必要な配送費などは、ネットショップ側で負担する必要はありません。
せっかく売れた商品が戻ってくるのは残念ですが、返品されたものを受け取り、代金も返せば対応は終わりです。
なお、返品された商品に破損・汚損がある場合は別問題です。破損・汚損の程度によって、返金しなければいけない額などは変わってくるでしょう。
トラブルを予防するには
「法定返品権」も踏まえた返品のルールを明示しておくことです。
法定返品権を認めないとするためには、法律に則った記載が必要です。
法的には、返品のルールの記載内容、場所、文字の大きさまで指定があります。
正確な記載をするにはやや面倒に感じるかもしれません。
しかし、法律に則った記載をすれば、法的にしっかり守られたネットショップ運営ができます。
キャンセルや返品、また商品に欠陥があった場合のルールは、やはり法的な観点から総合的に策定しておくことが必要です。
弁護士への法律相談(初回30分無料)はこちらから。
【関連記事】
【ネットショップ側】顧客から注文をキャンセルしたいと言われたら?
【ネットショップ側】ショップ開設にあたって、気を付けるべき法律は?
【ネットショップ側】広告規制の考え方
【ネットショップ側】契約はいつ成立する? 契約成立するとどうなる?