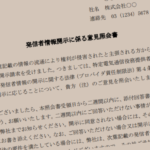プライバシー権侵害の開示請求 拒否する場合の「不同意の理由」書き方を解説
「侵害された権利」の欄に「プライバシー権」と書かれた意見照会を受け取ったときの、拒否(不同意)の理由の書き方について解説しています。
名誉毀損の成立要件
法律上、プライバシー権が成立するためには、以下の要件が必要です。
① 特定性(同定可能性)がある
② プライバシー権侵害成立の三要件が認められる
③ 違法性阻却事由がない
この①~③いずれかが認められない場合にはプライバシー権侵害は成立しません。そのため、開示請求を拒否(開示に同意しないと回答)する際は、このいずれかが認められないことを拒否の理由に記載することが有効です。
特定性(同定可能性)がないこと
プライバシー権侵害が成立するためには、その投稿が「開示請求者のことを指している」といえることが必要です(このことを「特定性(ないし同定可能性)」といいます。)。
そのため、「誰のことを指しているかわからない」あるいは「他の人のことを言っているとも読める」という場合には、特定性が認められず、名誉毀損は成立しないことになります。
書き方はケースによってまちまちですが、記載例としては以下のようなものになります。
- 投稿の対象者について、何も情報(氏名、性別、所属など)が書かれておらず、誰のことを言っているか読み取れない
- 「Wさん」とイニシャルが書かれているだけで、「W」に該当する人は複数いる
- 「経理部の女」と書かれているが、経理部の女性従業員は複数いる
- 「あのデブ」とだけ書かれているが、ふくよかな方は大勢いる
ただし、特定性は前後の文脈も含めて判断されます。
そのため、単にその投稿に書かれたものが「源氏名や伏字、イニシャルだけ」という主張だけでは特定性が否定されるとは限りません。
開示請求者側も、何か根拠があって「自分のことだ」と思っているわけですから、特定性の点で反論する場合は説得的な記載が必要になります。
プライバシー権侵害の要件が認められないこと
プライバシー権侵害は、一般的には次の3つの要件すべてがそろっている場合に成立するとされています。(プライバシー権侵害の要件について難しい議論はありますが、ここでは分かりやすさを優先した説明をしています。)
- 私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがらであること
- 一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められることがらであること
- 一般の人々に未だ知られていないことがらであること
そのため、反論としては、これらのどれかが認められないという内容になります。
- 「○○」と書かれているが、「○○」すること自体は違法・不正な行為ではないし、公開されることで羞恥心を覚える内容でもない(②)
- 「○○」というのは、自分自身で公開していた内容であって、一般の人々に未だ知られていないとはいえない(③)
違法性阻却事由がある
違法性阻却事由というものがあると、プライバシー権侵害は成立しません。
プライバシー権侵害の場合、一般的には次の内容が認められれば違法性阻却事由があると考えられています。
その事実を公表する理由が公表されない法的利益に優越する場合
これをどう判断するかですが、様々な要素を総合して判断するとされています。
これまでの判例で例示された考慮要素は、次のようなものです。
- 公開された情報の性質や内容
- 情報が伝達される範囲
- 被害者が被る具体的な被害の程度
- 被害者の社会的地位
- 公開されたときの社会的状況や、その後の変化
- 情報を公開する必要性
- 公開された媒体の性質
これらの記載例は、以下のとおりです。
- 公開された情報の内容は「○○」というものであり、性質上必ずしも秘匿性の高いものではない(①)
- 情報の伝達範囲は、この掲示板の閲覧用パスワードを知るものに限られる。一般に公開されているわけではないから、その伝達範囲は広いとはいえない(②)
- ○○氏の負う不利益は、不快感程度のものである(③)
- ○○氏は●●という公益に関わる活動をしており、その社会的影響力も大きい(④)
- ○○氏は●●という公益に関わる活動に現実に従事しており、現在もその地位にある(⑤)
- ○○氏の活動は公の評価を受るべきものであり、公開された情報はその評価のため必要な情報である(⑥)
- 公開された媒体はニュースサイトであり、ゴシップサイトのようなものではない(⑦)
もっとも、これが認められるのは犯罪報道(逮捕や起訴の報道)や、公権力を行使する公務員(知事や議員など)の問題行為の公開などのケースに限られます。
単に大衆の興味を満たすような内容では違法性は阻却されないので注意しましょう。
プライバシー権侵害のケースでの拒否理由の書き方の説明は以上のとおりですが、もちろん具体的な記載はケースによって違いますし、実際に文章にするのが難しい場合もあると思います。
意見照会書への回答について相談されたい方は、当事務所にぜひ一度お問い合わせください。
弁護士に依頼できることや費用の目安等についてはこちらをご覧ください。
発信者情報開示請求について、発信者側の解説記事についてはこちらをご覧ください。
名誉毀損の開示請求 拒否する場合の「不同意の理由」書き方を解説
「侵害された権利」の欄に「名誉権」(名誉毀損)と書かれた意見照会を受け取ったときの、拒否(不同意)の理由の書き方について解説しています。
名誉毀損の成立要件
法律上、名誉毀損(民事)が成立するためには、以下の要件が必要です。
① 特定性(同定可能性)がある
② 投稿によって社会的評価が低下した
③ 違法性阻却事由がない
この①~③いずれかが認められない場合には名誉毀損は成立しません。そのため、開示請求を拒否(開示に同意しないと回答)する際は、このいずれかが認められないことを拒否の理由に記載することが有効です。
特定性(同定可能性)に対する反論
名誉毀損が成立するためには、その投稿が「開示請求者のことを指している」といえることが必要です(このことを「特定性(ないし同定可能性)」といいます。)。
そのため、「誰のことを指しているかわからない」あるいは「他の人のことを言っているとも読める」という場合には、特定性が認められず、名誉毀損は成立しないことになります。
書き方はケースによってまちまちですが、記載例としては以下のようなものになります。
- 投稿の対象者について、何も情報(氏名、性別、所属など)が書かれておらず、誰のことを言っているか読み取れない
- 「Wさん」とイニシャルが書かれているだけで、「W」に該当する人は複数いる
- 「経理部の女」と書かれているが、経理部の女性従業員は複数いる
- 「あのデブ」とだけ書かれているが、ふくよかな方は大勢いる
ただし、特定性は前後の文脈も含めて判断されます。
そのため、単にその投稿に書かれたものが「源氏名や伏字、イニシャルだけ」という主張だけでは特定性が否定されるとは限りません。
開示請求者側も、何か根拠があって「自分のことだ」と思っているわけですから、特定性の点で反論する場合は説得的な記載が必要になります。
社会的評価の低下に対する反論
名誉毀損が成立するためには、その投稿によって「社会的評価の低下したこと」が必要です。(社会的評価の低下とは聞きなれない言葉だと思いますが、「世間のイメージ・印象が悪くなる」程度の意味です。)
そして、社会的評価が低下は、(ネガティブな内容の)具体的事実が指摘されたときに発生すると一般的に考えられています。つまり、具体的事実の指摘がない、単なる意見だけでは基本的に社会的評価は低下しないと考えられています。
そのため、社会的評価の低下に対する反論としては、「具体的事実の記載がない(単なる意見である)」という主張が考えられます。
- 「ワンマン社長」と書かれているが、「ワンマン」経営それ自体は悪いことではない
- 「料理がまずい」と書かれているが、単に感想を書いただけで社会的評価が低下するとまではいえない
- 「ムカつく」と書いたが、単に主観を言っただけ
また、投稿記事の記載を不自然に解釈し、具体的事実の指摘があると主張されることがあります。そのような場合は、投稿記事の記載を読んだときの「自然な解釈」を反論として説明するのが効果的です。
開示請求者は、投稿記事のうち「料理が美味しくなかった」という記載について「腐った材料を提供しているという事実の指摘である」と主張しています。しかし、そのような解釈をすることは不自然であるといえます。この記載は、料理を実際に食べた客の「美味しくなかった」という意見を述べたに過ぎないと解釈することが自然です。
違法性阻却事由がある
違法性阻却事由というものがあると、名誉毀損は成立しません。
名誉毀損の場合、次の3つの要件すべてが認められれば違法性阻却事由があると判断されます。
- 表現の内容が公共の利害に関することがらであること
- その表現がもっぱら公益を図る目的でなされたこと
- 摘示された事実が真実であるか、真実と信じたことについて相当の理由があること
このうち、発信者情報開示請求との関係で最も重要なのは③であり、③を説明することで十分なケースが多いといえます。
ただし、③を効果的に説明するためには、証拠の提出を考える必要があります。
開示請求が任意請求の場合は証拠がなくても非開示にできるかもしれませんが、裁判になっている場合は証拠の提出がなければ厳しいといえます。
また、書き方としては、単に「投稿内容は真実である」と書くだけでは弱いでしょう。5W1Hを意識し、時系列で整理すると説得的な文章となります。
さらに、報道などを根拠にしたのであれば、実際の報道内容を指摘することも必要です。
- ○○年○○月○○日○○時ころ、A部長がB係長に対し、○○株式会社の3階の会議室で「お前は能無しだ、クビにしてやる」などと怒鳴りつけていた
- ○○新聞の○○年○○月○○日付のニュース記事で、開示請求者が○○していたことが報道されている
名誉毀損のケースでの拒否理由の書き方の説明は以上のとおりですが、もちろん具体的な記載はケースによって違いますし、実際に文章にするのが難しい場合もあると思います。
意見照会書への回答について相談されたい方は、当事務所にぜひ一度お問い合わせください。
弁護士に依頼できることや費用の目安等についてはこちらをご覧ください。
発信者情報開示請求について、発信者側の解説記事についてはこちらをご覧ください。
身に覚えのない発信者情報開示請求(意見照会書)が届いたときの対処法を弁護士が解説!
意見照会書が届いたけれども、全く身に覚えがないというケースも珍しくありません。
この記事では、身に覚えのない投稿についての意見照会書が届いたときはどう考えたらよいか、またそのときの対処法について解説しています。
なお、BitTorrent(トレント)などのファイル共有ソフトの使用に関して意見照会書を受け取った方は、こちらの記事もご覧いただければと思います。
また、BitTorrent(トレント)などのファイル共有ソフトの使用に関して過去の逮捕事例はこちらで紹介しています。
「何かの間違い」の可能性は低い
投稿に身に覚えがない場合、何かの間違いだと考える人がほとんどです。
しかし、意見照会書を送る際にはプロバイダは十分確認しますから、プロバイダの手違いで送られるということは考えづらいです。
その投稿にご自身の契約している回線が使用されたと考えるべきでしょう。
「回線を使用できる人」が使用したと考える
ご自身が投稿していないとすれば、回線を使用できる人が投稿したと考えるのが妥当です。
例えば、家庭の回線であれば、同居の方かもしれませんし、Wi-Fiのパスワードを教えた友達かもしれません。
会社の回線であれば社員の方が考えられます。
なお、古いWi-Fiルーターには、アクセスするためのパスワードが設定されていないものも一部あったようです。
使用者がそのことを知らず、無断で投稿に使用されたという例もありますので、念のためお使いの機種がそのようなものでないかも確認する必要はあるでしょう。
個人情報は開示されてしまうか
残念ながら、ご自身が投稿していないことを証明しても、開示を防ぐ効果はありません。
開示の要件が認められる限り、相手に情報は開示されてしまいます。
見知らぬ人に自分の情報が伝わることに抵抗がある方がほとんどだと思いますが、法律の仕組みがそのようになっている以上、やむを得ないところです。
以上を踏まえ、身に覚えがない開示請求が届いたときの対処法について説明します。
身に覚えがない発信者情報開示請求への対処法
①まず開示請求が認められるケースかどうかを検証する
さきほど、拒否(不同意)の回答をしても開示されるという結論には変わりないと説明しましたが、あくまでこれは「開示請求の要件が揃っている」ことが前提です。
開示請求の要件が認められない(例えば、権利侵害が認められない)ケースの場合、不同意(拒否)の回答をすれば、こちらの情報は開示されません。
そのため、身に覚えのない開示請求であっても、開示請求が認められるものであるかどうかは念のため検証する必要はあるでしょう。
実際に開示が認められるかどうかはケースバイケースの判断ですが、こちらの記事では、どのような投稿が開示の対象となるのかの一般的な判断基準について解説しています。
②同意・不同意(拒否)どちらの回答をするか決定する
①で検討した結果をもとに、同意・不同意(拒否)どちらの回答をするか決定します。
開示請求が認められると判断できる場合
この場合は、開示に同意し、早めに「自分が投稿者でないこと」を説明して理解してもらうことが早期解決につながります。
とはいえ、見知らぬ人に個人情報が開示されることに抵抗がある方も少なくないと思われます。
そのような方は、とりあえず不同意(拒否)の回答を行うのもひとつの手です。
特に、今回の開示請求が任意請求である場合、プロバイダはこちらが同意の回答をしない限り個人情報を開示しません。
プロバイダが任意で開示しない場合、開示請求者はプロバイダを相手に裁判をする必要があります。
しかしこのとき、開示請求者が裁判までは行う気はないということもあります。
この場合、こちらの情報は開示請求者に伝わらずに終了しますから、このような幸運なケースを期待して不同意(回答)を行うこともあります。
なお、任意請求や裁判の区別、任意請求がなされる理由などについて詳しくは以下の記事で解説しています。
開示請求が認められない、又は微妙なケースと判断できる場合
この場合は、不同意(拒否)の回答をすることをお勧めします。
結果的に開示請求が認められなければ、こちらの個人情報が開示されることはないからです。
また、仮に見通しが外れて開示請求が認められたとしても、開示された後に「自分が投稿者でないこと」を説明すれば十分ということもあります。
③(開示された後)投稿者でないことを説明する
開示された後は、面倒でも自分が投稿者でないことを説明する必要があります。
回線契約者と投稿者が違う場合は、原則として回線契約者が責任を負うことはありません。
しかし、回線契約者は日常的にその回線を使用しているでしょうから、その投稿をしたと最初に疑われるのは回線契約者です。
そのため、行ってもいない投稿で責任を負うことを防ぐために、ご自身が投稿者でないことをしっかり説明する必要があるのです。
自分が投稿者でないことを示す事情については、例えば次のようなものが考えられます。
・被害者と面識・関わりがない
(例:被害者の知人・同僚・顧客などではない、被害者(会社)の従業員でない など)
・誹謗中傷をする動機がない
(例:被害者とトラブルになったことはない など)
・その投稿を行う可能性がない
(例:投稿内容は男性目線で書かれているが、自分は女性である など)
・他に投稿者がいる可能性がある
(例:Wi-Fiにパスワードがかかっていなかった、パスワードを見やすいところに掲示していた など)
逆に、これらの事情を全く説明できない場合、単に「身に覚えがない」と言い訳しているに過ぎないとされてしまう可能性があります。
そうなってしまうと法的責任を負うことは免れませんので、やはり自分は投稿者でないことは丁寧に説明する必要があるでしょう。
投稿者でない回線契約者が責任を負うパターンとは
回線契約者と投稿者が違うケースでも、次の場合には例外的に責任を負う可能性もあります。
- 会社の回線が使用されたケースで、投稿内容が競合他社を貶めるものであった場合
- 違法な投稿に使用されることがわかっていてあえて回線を貸したような場合
とはいえ、責任を負うのは例外的であって、「回線契約者も名義がある以上共犯だ」といった乱暴な議論で責任を負わされることはありません。
当事務所では、発信者側での発信者情報開示請求対応に多数の実績があります。
発信者情報開示請求を受けたけども対応を相談されたいという場合は、ぜひ一度お問い合わせください。
弁護士に依頼できることや費用の目安等についてはこちらをご覧ください。
発信者情報開示請求について、発信者側の解説記事についてはこちらをご覧ください。
不正インストールを疑われたときに弁護士に依頼できる内容や費用の目安は?
ソフトウェアメーカーやBSA、ACCSなどの団体から、ソフトウェアの不正利用(不正インストール)を指摘する通知が届いたとき、弁護士に相談・依頼を検討する方も多くいらっしゃいます。
ただ、弁護士に相談・依頼することで具体的にどんなメリットがあるか、また、そもそもどんなことを依頼できるかよくわからないことも多いと思います。
この記事では、ソフトウェアの不正利用(不正インストール)を指摘する通知を受けた方が弁護士に相談・依頼できることとそのメリットについて解説しています。
この記事はこんな人におすすめ
- ソフトウェアの不正利用(インストール)があると指摘する通知が届いた方
- 弁護士への相談・依頼を検討されている方
- 弁護士への相談・依頼にどのようなメリットがあるか知りたい方
① 見通しを立てることができる
ほとんどの方にとって、不正インストールの通知が来るのは初めての経験です。そのため、今後どうなっていくのか不安になる方がほとんどだと思います。
そのような不安を解消し、良い形での紛争解決を目指すためには、現状の分析と今後の見通しを確認することが不可欠です。以下の各事項の見通しを立てることで、適切な方針を立てることができます。
不正インストールの件で検討すべき見通し
- 自社が著作権侵害の責任を負うか
- 示談金の額
- 紛争解決までの期間
- 他に波及しうるトラブルの有無 など
当事務所では、不正インストールのケースについて豊富な経験があります。これまでの経験に基づき、精度の高い見通しと適切な対応方針についてアドバイスを提供することが可能です。
法律相談料
5,500円/30分あたり(税込・初回30分は無料)
② 調査回答書の作成依頼
特にBSAやACCSからの通知では、まずこちら側がソフトウェアのインストール状況について調査し、その調査結果を報告するよう要請されるのが一般的です。
不正インストールが疑われたケースでは、初回の回答が最も重要であると言っても過言ではなく、その回答内容によっては決定的に不利になることも珍しくありません。
しかし、どのように調査したらよいか、また調査結果をどのように回答するのがよいかわからない場合も多いと思います。当事務所では、これまでの経験に基づき、不利にならない回答書を作成することが可能です。
そのため、弁護士に依頼するかどうかにかかわらず、回答をする前に一度弁護士に相談されることを強くお勧めします。
調査回答書作成費用
着手金:220,000~(税込)
成功報酬:0円
>>「BSAからの」通知書への対応方法については以下の記事で解説しています。
③ 示談交渉の代理
弁護士に依頼することで、相手方とのやりとりを任せることができます。
相手方との交渉による負担は想像以上に大きいものですが、弁護士に交渉を任せることで、時間的・精神的負担を大幅に軽減することができます。
また、示談交渉における示談金の減額交渉や分割払いの交渉は法律に基づくものであり、法律にのっとったやりとりが必要です。
弁護士に依頼することで、法律に基づく交渉ができますから、最終的な示談の内容を納得のいくものとすることが可能です。
示談交渉依頼費用
着手金:220,000~(税込)
成功報酬:220,000円~(税込)
※調査回答書の作成を含む価格です。
>>不正インストールに関する示談については以下の記事で解説しています。
④ 立入調査・証拠保全への立ち会い
不正インストールが疑われるケースでは、ソフトウェアメーカー側から立入調査の要請がなされたり、証拠保全が実施されることがあります。
これらはいずれも事業所の現地調査であり、現場で適切な対応をとる必要があります。現場に弁護士が立ち会うことで、立入調査・証拠保全へも適切な対応を行うことができます。
立入調査・証拠保全への立ち会い費用
110,000円~(税込)
お気軽にお問い合わせください
四谷コモンズ法律事務所では、相談に来られた方にとって最良と考えるアドバイスをご提案いたします。
弁護士がご依頼いただく必要がないと考えるときは、ご相談のみ終了することも多くあります。無理に依頼を勧めたりすることはいたしません。
現在の状況を整理するだけで、ご不安が解消することもあります。
ご心配事やご相談したいことがある場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
当事務所では、不正インストールの通知が来たケースの対応に豊富な実績があります。
ご心配事やご相談したいことがある場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
何が行われる?不正インストールが疑われたときの証拠保全や立入調査【弁護士解説】
ソフトウェアの不正利用(不正インストール)の事案では、事業所への任意の立入調査や証拠保全が実施されることがあります。
いずれも事業所への立入調査ですが、実際はどのようなことが行われているか気になる方も多いと思います。
そこでこの記事では、ソフトウェアの不正利用(不正インストール)の事案における任意の立入調査や証拠保全について解説します。
この記事はこんな人におすすめ
- ソフトウェアの不正利用(インストール)があると指摘する通知が届いた方
- 任意の立入調査の要請を受けている方
- ソフトウェアの不正利用が疑われたときの任意の立入調査や証拠保全について知りたい方
>>「ソフトウェアメーカーからの」通知書への対応方法については以下の記事で解説しています。
>>「BSAからの」通知書への対応方法については以下の記事で解説しています。
任意の立入調査とは
任意の立入調査は、事業者の同意に基づいて行われる事業所への立入調査です。
ソフトウェアの利用規約に、メーカーの立入調査の権利を規定したものはありますが、それでも強制的に事業所に押し入りPCを検査・押収するような権限はありません。そのため、あくまで調査の対象となる事業者の同意が必要になります。
任意調査の要請に応じる場合は、事前にソフトウェアメーカー側と日程調整をします。また、事業に影響が出ないよう、土日や祝日に実施されることもあります。
立入調査を実施するのはあくまでメーカーの社員や代理人弁護士であって、裁判所がこれに介入することはありません。
証拠保全とは
証拠保全は、裁判所が認める立入調査です。
証拠保全が認められるためにはメーカー側が裁判所に申立を行い、事業所内での不正利用の疑いがあることを証拠によって認めてもらう必要があります。
立入調査を拒むことによる罰則などはありませんが、合理的な理由による拒否でない限りその後の裁判で不利に働く可能性が十分にあります。
証拠保全が実施される場合は、実施の1~2時間前に裁判所の担当者から連絡があります。この間に対応を検討することは非常に難しいものがありますから、証拠保全を受ける可能性がある場合には、すぐに相談できる弁護士を事前に探しておくことが重要です。
なお、立入調査の場合、メーカー側の代理人弁護士のほか、裁判官も現場に来ることが一般的です。
調査の方法はどういうものか
任意調査も証拠保全も、基本は写真撮影です。
ソフトウェアのインストール状況やMACアドレス等をモニター画面上に表示し、それを写真に収める形です。
調査は基本的に事業所内にあるすべてのPCが対象になります。
ソフトウェアにもよりますが、写真撮影はPC1台につき10分~30分程度かかりますから、調査対象のPCの台数が多い場合、調査終了までかなりの時間がかかります。
調査後の流れ
調査の結果、不正インストールの形跡が見当たらなければ、基本的にはそれ以上の追及はありません。
まれに不正インストールの形跡が見つからなかったにもかかわらず、請求を続けるメーカーもあります。しかし、証拠が見つからなかったという事実は疑われた側にとっては有利に働きます。その意味で、立入調査を受け入れることは、疑われた側にとってもメリットがある場合があります。
一方、不正インストールの形跡が見つかった場合は、それに基づいた示談交渉がなされます。この場合、不正インストールの証拠が見つかったわけですから、示談交渉を突っぱねると裁判などの法的手続に移行する可能性が高いでしょう。
当事務所では、不正インストールの通知が来たケースの対応に豊富な実績があります。
ご心配事やご相談したいことがある場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
ソフトの不正インストール|示談金の額や減額の可能性について解説
ソフトウェアメーカーや、BSA、ACCSなどの団体から不正利用(不正インストール)の通知が届くというケースが多くあります。
そのような通知をきっかけに示談交渉が開始されることも多いですが、最終的に成立する示談がどのようなものになるか、気になる方も多いと思います。
そこでこの記事では、ソフトウェアの不正利用が発覚したケースでの示談金の額はどのようなものか、減額の可能性はあるのかについて解説しています。
この記事はこんな人におすすめ
- ソフトウェアの不正利用(インストール)があると指摘する通知が届いた方
- 不正利用が発覚したケースでの示談金の額の計算方法が知りたい方
- ソフトウェアの不正利用で莫大な示談金の請求を受けている方
>>「ソフトウェアメーカーからの」通知書への対応方法については以下の記事で解説しています。
示談金の計算方法
法律的には、ソフトウェアの不正インストールは著作権侵害であり、民法上の不法行為に該当します。
このときに請求される損害の項目は、以下のものが一般的です。
- 著作権侵害による損害
- 弁護士費用
- 遅延損害金
これらを順番に解説していきたいと思います。
① 著作権侵害による損害
著作権侵害による損害は、基本的には次のように計算されます。
ソフトウェアの小売価格はある程度客観的に決まっているので、示談で最も問題になるのは不正インストールの件数でしょう。
この件数は、こちらが不正インストールを認めた場合はその件数、認めなかった場合は証拠保全や任意調査で確認できた件数になることがほとんどです。(その他、不正インストールの告発をした人の情報から認定するということも考えられますが、告発した人が確たる証拠を提出していない限り、この件数で認定されることはないと思われます。)
>>ソフトウェアの不正利用に関する立入調査や証拠保全についてはこちらの記事で解説しています。
② 弁護士費用
ここでいう弁護士費用は、損害賠償請求にかかった弁護士費用です。
基本的に、裁判で認められるのは、①で認められる金額の10%です。つまり、著作権侵害による損害が100万円であれば弁護士費用は10万円となります。
実際に著作権者が弁護士に支払ったのはこれより多い金額かもしれませんが、ほとんどの裁判例では10%に限り認められていますので、示談の場面でも最終的にはこれに従って計算されることが一般的です。
③ 遅延損害金
遅延損害金は、法的には不正インストールを行ってから実際に損害賠償を支払うまで年3%で計算されます。
例えば、①著作権侵害による損害が100万円の場合、②弁護士費用は10万円になります。そして、不正インストールがあった日から実際に損害賠償を支払うまでがちょうど1年だとすると、遅延損害金は3万3000円になります。
この場合、示談金の額は113万3000円となるということになります。
金銭以外の条件
示談の際は、ソフトウェアメーカー側が示談書を提示することが一般的です。そのような示談書には金銭の支払い以外にも、以下のような条件が記載されています。
著作権者側から提示される示談書は分量がかなり多いこともあります。その文書チェックについては弁護士に依頼することも有用です。
示談金の額を減額することはできるか
不正利用していたソフトウェアが業務用の非常に高価なものである場合や、不正インストールの件数が非常に多い場合などでは、請求される金額が莫大なものになるケースも珍しくありません。
そして、示談金額は上記のとおりある程度機械的に計算されるため、示談金の額を減額することは簡単ではありません。
とはいえ、計算の根拠となった小売価格や不正インストールの件数が著作権者側にとって不当に有利に設定されていることがあります。また、そもそも著作権者側が把握している不正インストールの事実が本当に正確なものかについても争う余地はあります。
その他、長期間の分割払いを認める示談が成立することもあります。
当事務所では、不正インストールの通知が来たケースの対応に豊富な実績があります。
ご心配事やご相談したいことがある場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
発信者情報開示請求を受けたときに弁護士に依頼できる内容や費用
この記事では、発信者の方が弁護士に相談・依頼することでどんなメリットがあるか、また、そもそもどんなことを依頼できるか、費用の目安について解説しています。
① 見通しについての法律相談
開示の是非は法律に基づいて判断されますが、実際に開示が認められるかどうかはケースバイケースの判断にならざるを得ません。
投稿そのものの内容だけでなく、前後の文脈なども判断材料になるからです。
ご自身の投稿はどのくらい開示される可能性があるかを弁護士に相談することで、精度の高い見通しを立てることができます。
そして、その見通しに基づいて今後の方針を立てることができますから、現在の漠然とした不安を解消することにもつながります。
| 法律相談料 | 5,500円/30分あたり(税込・初回30分は無料) |
② 意見照会に対する回答書の作成依頼
開示請求を受けたとしても、発信者側にも言い分があることは多いです。
そして、こちらの言い分がしっかり伝われば非開示にできるケースも少なくありません。
ただ、開示請求が法律に基づくものである以上、それに対する反論も法的に整理されたものでなければいけません。
こちら側の言い分や証拠を雑多に出しても、裁判所はこちらの意図を十分にくみ取ってはくれません。
弁護士に回答を依頼することで、法的に整理された形でこちらの言い分を裁判所に届けることができ、非開示の判断が出る可能性を上げることができます。
また、プロバイダとのやりとりも弁護士に任せることができますので、プロバイダとのやりとりに不安があるという場合も安心できます。
当事務所では、回答書(意見書)の作成による非開示の実績が多数ございます。代表的なものは以下の記事で紹介しています。
| 意見書作成費用 | 着手金 | 成功報酬 |
| 任意請求の段階 | 165,000円~(税込) | 0円 |
| 裁判の段階 | 165,000円~(税込) | 165,000円(税込) |
※対象となっている投稿の数などで費用は増減することがあります。
③ 示談交渉の代理
開示の可能性が高いと判断された場合や、実際に開示されてしまった場合は、示談について検討することになります。
弁護士に示談について相談することで、示談の見通しや、示談金の相場について知ることができます。
また、示談交渉を弁護士に依頼することで、相手方とのやりとりを任せることができます。
相手方との交渉は、専門家でなければ難しいものですし、本人の負担も想像以上に大きいものです。
弁護士に交渉を任せることで、このような負担を軽くすることができます。
| 示談交渉の代理 | 着手金 | 成功報酬 |
| 132,000円~(税込) | 165,000円~(税込) |
※対象となっている投稿の数などで費用は増減することがあります。
お気軽にお問い合わせください
四谷コモンズ法律事務所では、相談に来られた方にとって最良と考えるアドバイスをご提供いたします。
弁護士がご依頼いただく必要がないと考えるときは、ご相談のみで終了することも多くあります。無理に依頼を勧めたりすることはいたしません。
現在の状況を整理するだけで、ご不安が解消することもあります。
ご心配事やご相談したいことがある場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
発信者情報開示請求について、発信者側の解説記事についてはこちらをご覧ください。
開示が認められても発信者側が損害賠償請求で勝訴する可能性は?
発信者情報開示請求によって開示に成功した側は、発信者に対して損害賠償を求める通知を送ってくることが一般的です。
ここから当事者間(被害者・発信者)の交渉が始まりますが、折り合いがつかなかった場合は、損害賠償請求の裁判に発展します。
開示後の裁判で発信者側に勝つことはあるのかを解説したいと思います。
全面勝訴することは難しい
開示請求の裁判を経て開示に至った場合は、問題となった投稿について裁判所が一度「違法」と判断したものといえます。
そのため、損害賠償請求の裁判でも、基本的には「違法」と判断されることがほとんどです。
ただ、「その投稿が違法かどうか」と「損害賠償の額がいくらか」は別の問題です。
投稿内容が違法であれば開示が認められますから、極端な話、損害賠償の額が100円であっても違法は違法なので開示は認められます。(開示請求の裁判では、損害の額は判断されません。)
したがって、損害賠償請求の裁判では、投稿が違法であることを前提に、損害賠償の額を可能な限り下げる方向で争うというパターンが多いといえます。
勝訴するケースとは?
とはいえ、中には全面勝訴に成功するケースもあります。
その理由として、次の2つが考えられます。
①開示請求の段階では裁判所の判断材料が違うことがある
先ほど、勝訴が難しいとした理由を「情報の開示に至った場合は、問題となった投稿について裁判所が一度「違法」と判断した」ためと説明しました。
しかし、開示請求の段階ではの裁判所の判断材料は限定されていることがあります。
発信者の言い分は、あくまで意見照会への回答として、プロバイダを通じて裁判所に提供されるだけだからです。
そして、意見照会への回答は、時間的、物理的な制約から、発信者が十分な回答ができないケースもあります。
また、発信者への意見照会は基本的に1回限りです。
開示請求者(原告)側は、回答書に記載された発信者の主張に対して反論することができますが、これに対して発信者がさらに反論をする機会はないのです。(プロバイダによっては開示請求者(原告)側の主張が出るたびに意見照会をしてくれるところもありますが、このような対応をしてくれるのはかなり少数です。)
一方、損害賠償請求の場合は、発信者側もその言い分が尽きるまで主張することができますし、開示請求者側の反論に対してさらに反論することも可能です。
このように、開示を判断するときと、損害賠償を判断するときで、裁判所にある判断材料は変わってくることがあるのです。
②開示請求と損害賠償請求では、判断する裁判官が違う
開示と損害賠償では、基本的に判断する裁判官も違います。
ある投稿内容が違法であるかどうか微妙なケースでは、裁判官の考え方によって結論が変わることがよくあります。
また、損害賠償請求について判断する裁判官が、開示請求の段階で投稿を「違法」と判断した裁判官に忖度するということもありません。
これら2つの理由から、開示請求の裁判では違法と判断された投稿が、損害賠償の裁判では適法と判断され、全面勝訴することもあるのです。
実際、私の担当した事件でも、損害賠償の裁判で全面的に勝訴したケースがあります。
開示されてしまった後は、方針決定が重要
発信者が全面勝訴するケースもあるとはいえ、基本的には多くないといえます。
そのため、自分の情報が開示されてしまったときは、全面勝訴を目指して争うのか、それとも損害賠償の額を可能な限り低くすることを目指すのかは慎重に見極めた方がよいでしょう。
当事務所では、発信者側での発信者情報開示請求対応に多数の実績があります。
発信者情報開示請求を受けたけども対応を相談されたいという場合は、ぜひ一度お問い合わせください。
発信者情報開示請求について、発信者側の解説記事についてはこちらをご覧ください。
インターネットの誹謗中傷における示談の相場を弁護士が解説
インターネットの誹謗中傷案件で、犯人が特定されたという報道はしばしば目にすることがあります。
しかし、その後はどうなったのか、示談はどのように行われたのかという情報は、守秘義務の問題もありなかなか知ることができません。
そこでこの記事では、ネット誹謗中傷における示談のよくあるパターンについて説明したいと思います。
ほとんどが金銭での解決
ネット誹謗中傷案件も法的な紛争です。
法的紛争は最終的には金銭で解決することがほとんどで、ネット誹謗中傷案件も例外ではありません。
つまり、ネット誹謗中傷案件も、加害者が被害者にお金を払って示談することが一般的です。
示談金の内容は?
ネット誹謗中傷案件では、損害として請求されるのは次の2つです。
- 犯人特定にかかった調査費用(弁護士費用)
- 慰謝料
このうち、①犯人特定にかかった調査費用(弁護士費用)は、犯人特定のために弁護士に対して実際に支払った金額です。
この額については何かルールがあるわけではありません。開示請求者と弁護士との契約で決まりますから、当然、安いところもあれば高いところもあります。
相場としては、50万円から100万円程度のところが多い印象です。
②慰謝料は精神的苦痛に対して支払われるもので、ケースによって変わってきます。
示談において請求されるのは数十万から100万円程度でしょうか。(ケースによってはこれ以上の場合もあります。)
以上の①と②を合わせ、被害者側からは投稿者に対してまずは100万円から300万円の請求がなされます。
実際の示談の相場は?
とはいえ、①の調査費用はともかく、②の慰謝料は請求時には相場より大きい金額が設定されるのが一般的です。
そのため、投稿者が代理人として弁護士を依頼した場合、基本的には示談金の減額交渉がなされることになります。
示談交渉を経由すると、減額を求める理由や状況にもよりますが、最終的には20万円~100万円の間で示談がまとまることがほとんどです。
なお、示談交渉が決裂すると裁判になりますが、交渉決裂の理由のほとんどが金額に折り合いがつかなかったというものになります。
①調査費用と②慰謝料以外に請求されるものはある?
示談交渉の際は、①と②のほかに、例えば「書き込みで売り上げが下がった」として売上減少額を請求したり、「人材採用・育成費用が余分にかかった」として人材採用費用を請求するようなパターンもあります。
しかし、これらはいずれも裁判では認められづらい傾向にあります。
そのため、示談の際もこれらの支払いについて合意されることは多くはありません。
その他の条件について
インターネット上の誹謗中傷案件で示談する場合は、金額以外にも取り決められることがあります。
例えば、今回の件について一切の口外をしないとか、今後お互い一切関わらないなどです。
また、投稿者からの謝罪もありますが、これは謝罪文を送ったりすることがほとんどです。
直接面会して頭を下げる、ということが行われるケースは多くはありません。
当事務所では、投稿者、発信者いずれの立場でも、開示後の示談交渉について多数の実績があります。
発信者情報開示請求を受けたけども対応を相談されたいという場合は、ぜひ一度お問い合わせください。
発信者情報開示請求について、発信者側の解説記事についてはこちらをご覧ください。
発信者情報開示請求の裁判におけるプロバイダの対応や回答書について
発信者情報開示請求の裁判では、被告は発信者本人ではなくプロバイダになります。
そのため、裁判ではプロバイダが被告として一定の対応を行います。
裁判でプロバイダは発信者のためにどのような活動をしてくれるのかを解説したいと思います。
プロバイダが反論するのは「自社のため」
プロバイダは、発信者に関する情報を保有していますが、これは個人情報に該当しますし、このような情報を気軽に公開してしまうとプライバシーを侵害したとされる可能性があります。
そのため、プロバイダが最も関心があることは、「自分が個人情報保護法違反やプライバシー侵害をしたと言われないこと」です。
開示請求の裁判を起こされたとき、しっかり反論しなかったために開示を認める判決が出てしまい、情報を開示してしまいました、となれば、そのプロバイダは個人情報保護法違反やプライバシー侵害と言われる可能性が高くなります。
この理由から、プロバイダは開示請求の裁判で非開示に向けた反論を行っているのです。
発信者のための反論という要素もあるかもしれませんが、メインはあくまで「自社のため」ということは理解しておく必要があるでしょう。
プロバイダの反論には限界がある
プロバイダは開示請求の裁判でも反論はしてくれますが、限界があります。
なぜなら、書き込みの内容について、プロバイダは具体的な事情を知らないからです。
そのため、法律の解釈や過去の裁判例との比較などの反論はしてくれますが、抽象的な内容がほとんどです。
例えば、「○○部長からパワハラを受けた」という書き込みについて開示請求の裁判が起こされたとしましょう。
この裁判で反論しようとしても、プロバイダは「○○部長」がパワハラを行っていたかどうかはわかりません。
そのため、プロバイダとしては「「パワハラ」というのは抽象的な言葉であり、また感じ方も人それぞれなので、「パワハラ」という言葉だけでは違法とはいえない」というような抽象的な反論しかできないことになります。
これ以上の反論をするとすれば、「○○部長」の身辺を調査するとか、関係者に話を聴くなどの証拠収集活動が必要となるでしょうが、プロバイダがそこまでする義務はありません。
発信者が提出する回答書が重要となる
一方、開示請求を受けたプロバイダは、発信者に対して意見照会を行うこととされています。
発信者がこの回答において具体的な反論を記載し、証拠資料もつければ、プロバイダはこれを参考にできます。
少なくとも、ほとんどのプロバイダは回答書や添付された証拠を裁判の証拠として提出しています。
この理由から、意見照会書を受け取った発信者は、反論や証拠をしっかりと用意し、プロバイダに提供することが重要なのです。
なお、プロバイダによっては、発信者の回答書を裁判に提出すらしないというところもあるようなので、この点は注意する必要があるでしょう。
(個人的には、これはプロバイダの善管注意義務違反として損害賠償の対象になると考えています。)
当事務所では、発信者側での発信者情報開示請求対応に多数の実績があります。
発信者情報開示請求を受けたけども対応を相談されたいという場合は、ぜひ一度お問い合わせください。
弁護士に依頼できることや費用の目安等についてはこちらをご覧ください。
発信者情報開示請求について、発信者側の解説記事についてはこちらをご覧ください。