電話番号検索サイトの口コミ|悪評や誹謗中傷の被害を受けたときの法的対処法
電話番号検索サイトとは
電話番号検索サイトとは、電話番号に関する情報が掲載されたサイトです。対象となる電話番号は、電話番号として成立し得るすべての数字の組み合わせの電話番号となります。
このようなサイトは、知らない電話番号から着信があったとき、発信元を確認する際に有用です。
代表的な電話帳検索サイトは以下のとおりです。
電話帳ナビ(https://www.telnavi.jp/)
JPナンバー(https://www.jpnumber.com/)
電話番号検索@迷惑電話チェック(https://meiwakucheck.com/)
しかし、電話番号検索サイトは一般ユーザーの投稿による情報を掲載していることから、掲載された情報によって悪評や誹謗中傷の被害を受けることがあります。
そこでこの記事では、電話番号検索サイトの口コミ投稿で被害を受けたときの法的対策について解説します。
電話番号検索サイトにおける権利侵害
電話番号検索サイトでは、一般ユーザーのクチコミ投稿を掲載しています。
ユーザーが投稿をする際は匿名でよく、個人情報の登録が必須というわけでもありません。
そのため、競合他社を貶めるものや、事実無根の悪評、誹謗中傷、プライバシーを侵害するようなものも存在するのも事実です。
権利侵害の口コミの例
- 詐欺商品を売りつける電話です
- 根拠もなく支払いを請求してきます
- 電話口で怒鳴りつけられた
- パワハラが横行するブラック企業です
- 〇〇(本名)の携帯電話です など
このような投稿を放置すると、営業活動や採用活動に支障が出たり、私生活の平穏を害するなど、深刻な被害をもたらす可能性があります。
有効な法的対策
権利侵害の口コミについては、法的措置を講じることが可能です。
取り得る法的措置は次のとおりです。
① 削除請求
削除請求は、権利侵害の口コミに対する法的措置として最初に検討されるものです。
削除請求では、電話番号検索サイトの管理者に対して掲載された情報の削除を求めることになります。
法的な権利侵害を根拠に削除請求をすることができ、仮にサイトの管理者がこれに応じない場合は裁判手続もとることができます。
② 発信者情報開示請求(犯人特定)
削除請求によって口コミが削除されても、その後に同様の口コミが投稿されることがあります。
こういったケースは少数の人間が繰り返し投稿していることが多く、投稿者を特定し直接法的措置を取ることで将来の被害を防止することが適切です。
発信者情報開示請求は、まずはサイト管理者に投稿者のIPアドレス等の開示を請求し、その後に経由プロバイダに対して投稿者の氏名住所などの情報を開示する流れとなります。
開示請求には裁判手続が必要ですが、2022年に新設された発信者情報開示請求の手続により、比較的短期間(最短で2~3か月程度)で開示できるケースも増えています。
③ (犯人特定後の)損害賠償請求
発信者情報開示請求により投稿者が特定された後は、その者に対して損害賠償請求を行うことが一般的です。
請求する損害賠償の額はケースによりますが、慰謝料やそれまでかかった弁護士費用を請求することになります。
示談交渉を経て示談になることも多く、その際は示談金の支払のほか、口外禁止や今後投稿しないことを示談書に規定することがほとんどです。
法的対策を弁護士に依頼することはできるか
電話番号は企業や個人に直接紐づく情報ですから、電話番号と関連して悪評や誹謗中傷の口コミを投稿されることは、極めて強い権利侵害であるといえます。
一方で、法的措置には専門の法的知識が必要であり、弁護士に依頼することが最もスムーズな解決につながるといえます。
当事務所では、電話番号検索サイトの口コミに関する削除請求や開示請求を承っております。
ご相談を希望される方は、ぜひ一度当事務所までお問い合わせください。
相談や対応の流れ
まずは電話やウェブサイト、LINE等から法律相談の申し込みをしていただきます。
電話もしくは面談・ウェブ会議にて当事務所の弁護士が相談内容についてヒアリング等をさせていただき、事件の見通しやお見積りを法律相談の際に説明します。
こちらから契約を強引に勧めることは一切なく、当日に契約する必要はございませんので、ご安心ください。
相談を受けてから実際に依頼することとなった場合には、相談者と弁護士との間に委任契約書を締結した後、着手金のお支払いをしていただきます。
当法律事務所の弁護士がサイトや経由プロバイダ、投稿者に対して法的請求や裁判手続を代理して行います。削除のみご希望の場合は削除完了をもって解決、開示請求をご希望の場合は開示請求者を行い、その後投稿者との示談交渉を行ったうえで、示談によって解決へと導きます。
よくある質問
- 時間はどれくらいかかりますか?
-
ケースによって異なりますが、目安としては以下のとおりです。
削除請求の場合:1か月以内
開示請求の場合:3か月~半年程度(請求の相手方の対応によって変動します)
- 他の法律事務所でできないといわれたケースでも相談することはですか?
-
もちろん可能です。特に削除請求については多角的な方法から検討いたしますので、解決の糸口が見つかる可能性もあると思います。
弁護士費用
電話番号検索サイトの投稿によって被害を受けた方について、当事務所では次のような費用で対応を承っております。
「証券訴訟」とは|制度の概要・投資家の勝訴可能性
「証券訴訟」とは
証券訴訟とは、有価証券報告書等の虚偽記載(粉飾決算など)によって上場会社の株価が下落した場合に、投資家が提起する損害賠償請求の訴訟をいいます。
証券訴訟における損害賠償請求の法的根拠は、民法709条の一般不法行為のほか、金商法18条1項(発行市場での株式取得者に対する責任)、同21条の2(流通市場での株式取得者に対する責任)があります。
平成16年改正前の旧証券取引法(現在の金融商品取引法)においては、虚偽記載に関する規定としては発行市場での株式取得者に対する責任のみがあり、流通市場での株式取得者に対する責任の規定はありませんでした。
平成16年改正によって、流通市場での株式取得者に対する責任の規定が新設されました。なお、当初発行会社の責任は無過失責任とされていましたが、その後の平成26年改正において過失責任に変更されました。
虚偽記載に関する民事責任が法定されている趣旨
虚偽記載に対する特別の民事責任が規定されているのは、開示文書の虚偽記載が証券市場の透明性・公正性を害するものとしてもっとも非難されるべきものだからです。
虚偽記載は、有価証券の発行体自らが、投資家の投資判断に影響を与える企業開示情報に虚偽の記載をすることによって公正な市場価格の形成を阻害するものであって、証券市場の仕組みそのものをゆがめてしまうものです。
そこで、民事手続による被害者の救済を通じて虚偽記載を抑止することを目的として、虚偽記載に対する特別の民事責任が規定されました。
虚偽記載の対象となる開示文書の範囲
以下の開示文書に虚偽記載がある場合に、証券訴訟の対象となります。(流通市場での株式取得者に対する責任を前提にしています)
- 有価証券届出書
- 発行登録書
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 四半期報告書
- 半期報告書
- 臨時報告書
- 自己券買付状況報告書
- 親会社等状況報告書
- (これらの訂正報告書)など
*目論見書は対象外です。
証券訴訟の相手方(被告)となる者
証券訴訟の相手方(被告)となる者、つまり虚偽記載について責任を負う者は以下のとおりです。(流通市場での株式取得者に対する責任を前提にしています)
- 会社
- 役員等(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者)
- 発起人
- 監査証明をした公認会計士または監査法人
証券訴訟の相手方になり得る者は以上のとおりですが、会社は無過失の立証責任を負うとされているなど、取扱いに違いはあります。そのため、会社に対する損害賠償は認められた一方、役員等に対する損害賠償は認められないという結論が生じることもあります。
投資家側の勝訴可能性
虚偽記載の内容や発生原因は会社内部の事情であり、証拠を得られないため投資家(原告)側が勝訴する余地はないのではないか、という疑問を抱く方もいらっしゃると思います。
しかし、上場企業の虚偽記載が発覚した場合は、調査委員会(第三者委員会)が組織され、その調査結果の報告書は公表されることが一般的です。
また、証券訴訟においては、先述のとおり会社の過失に関する立証責任は転換されており、一部の投資家については損害額の推定既定もあります。
そのため、虚偽記載が発覚したケースでは投資家側が勝訴する可能性も決して低いものではありません。近年でも、東芝の粉飾決算について個人投資家に対する賠償を認める判決が相次いで出されております。
参考記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE22A180S4A320C2000000(不正会計、東芝に賠償命令 個人株主へ4800万円)
ネットの誹謗中傷は削除できる?削除方法や削除までの期間を解説
ネットの誹謗中傷は削除できるか
インターネットやスマートフォンの普及により、誰でも気軽に情報発信をすることが可能になりました。
しかし、実際はポジティブな内容の情報発信ばかりではなく、ネガティブな内容もあり、事実無根の内容で一般読者に間違った認識を与えるような情報も多く掲載されています。
違法な投稿を行った者(投稿者)に対して、被害者はその情報の削除を請求することが可能です。しかし、インターネットの情報は匿名での投稿も多く、投稿者が不明というケースも多くあります。
そのような場合の、ネットの誹謗中傷を削除する方法について解説します。
ネットの誹謗中傷の削除方法
削除請求の相手方
削除請求は、次の3者のいずれかに対して行うことが考えられます。
削除請求の相手方
- ① 投稿者
- ② 違法な情報を掲載しているサイト管理者
- ③ 違法な情報を掲載しているサーバーの管理者
① 投稿者
投稿者は、自身の投稿した内容が権利侵害になる場合、それを削除する義務を負うことになります。
しかし、先述のとおりネットでは匿名で投稿されるケースも多く、投稿者に対して削除請求ができない事例もあります。
このような場合は、発信者情報開示請求を行い投稿者を特定することで、本人に対する削除請求を行うことができます。
もっとも、サイトによっては自己投稿を削除できないケースも珍しくありません。このような場合は原則として投稿者に対する削除請求を行うことは適当でないといえます。
② 違法な情報を掲載しているサイト管理者
違法な情報を掲載しているサイトの管理者も、請求を受けた際は削除する義務を負うことになります。
投稿の削除だけが目的の場合は、この方法を選択することが一般的です。
③ 違法な情報を掲載しているサーバー管理者
違法な情報を掲載しているサイトがレンタルサーバーを利用しているような場合は、そのレンタルサーバーの管理者に対して削除請求を行うことができます。レンタルサーバーも違法な情報を掲載している者であることに変わりはないからです。
ただし、サイトがCDNサービスを利用している場合などは、利用しているサーバーがすぐには判明しないというケースもあります。このような場合は、この③の方法は適切でないことも少なくありません。
削除請求の方法
削除請求の方法は、以下の2点があげられます。
2つの削除請求の方法
- 1 任意請求
- 2 裁判
それぞれについて解説していきます。
1 任意請求
⑴ 投稿者に対する任意請求(投稿者が特定されている場合)
任意請求とは、裁判の手続によらずに行う(削除の)請求をいいます。
投稿者に対する削除請求は、基本的には内容証明郵便を送付することで行います。
損害賠償も併せて請求することもでき、その場合は同じ内容証明郵便の通知書に削除請求と損害賠償請求の文言を併せて記載します。
交渉をしても投稿者が削除に応じない場合は、2の裁判を選択することになります。
ちなみに、違法な投稿を行ったアカウントに対して、DMなどの方法で削除請求を行う方法も考えられます。しかし、この方法は注意が必要です。
というのも、DMで削除請求を行うことは、相手に「開示請求が未了である」ということが伝わることを意味します。
そうすると、「開示請求を行う意向がない(又は不可能)のではないか」という認識を与える可能性があり、削除に応じないばかりか、かえってDMをスクショされて晒されるなどの二次被害が発生する可能性もあります。また、証拠隠滅をしたうえで、開示請求を受けないような誹謗中傷が改めて投稿されるといった被害も考えられます
そのため、DMなどで削除請求を行う場合であっても、開示請求の準備を完了させたうえで行うことが無難でしょう。
⑵ サイト管理者・サーバー管理社に対する任意請求
実務上は、「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」という書面を郵送して行うのが一般的です。
発信者情報開示請求書の書式はプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会のHPで公開されています。
郵送で発信者情報開示請求を行える点で任意請求はメリットがあります。
また、任意請求に応じて削除に応じる投稿者、サイト管理者やサーバー管理者も多くあります。
もっとも、削除請求の際は、その理由となる法的根拠を説明しなければならず、それが曖昧であったりすると、削除請求に応じないこともあります。
また、任意の削除請求には原則として応じないというサイトもありますので、そのような場合は2の裁判を選択するほかありません。
2 裁判
削除請求は、裁判の形で行うこともできます。
裁判所が開示を認めると判断した場合は、相手方はその判断に従って投稿を削除することになります。
一口に裁判といっても、削除請求の関係では更に2つの手続に分けられます。
削除請求における裁判の種類
- (1)仮処分
- (2)通常訴訟
(1) 仮処分
仮処分は、通常訴訟よりも早く審理が終わるという点でメリットがあります。
そのため、基本的には削除請求の裁判は仮処分の方法で行われることになります。
もっとも、担保金を供託しなければならないとか、原則として損害賠償請求を併せて行うことはできないという点には留意する必要があります。
(2)通常訴訟
通常訴訟は、削除だけの目的であれば選択されることはあまりありません。
削除だけでなく、投稿者やサイト管理者に対する損害賠償請求も同じ裁判手続で行う場合に選択される手続となります。
なお、2022年に新設された発信者情報開示命令申立の手続は削除請求には利用することができません。
削除までの期間
削除請求を行ってから削除が行われるまでの期間は、削除請求の相手方や選択する手続によって違ってきます。
それぞれの期間は、概ね以下のとおりです。
1 任意請求
投稿者に対する削除請求
3日から1か月程度
サイト管理者に対する削除請求
1か月程度
サーバー管理者に対する削除請求
1か月程度
2 仮処分
1~2か月程度
3 裁判
6か月から1程度
まとめ
以上が削除請求の手続の説明です。
当事務所では、誹謗中傷の削除請求の実績が豊富にあります。
ネット誹謗中傷の削除請求についてお困りの方は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。
発信者情報開示請求とは?手続の流れ・方法・犯人特定までの期間について解説
発信者情報開示請求とは
発信者情報開示請求とは、インターネット上の匿名の投稿によって権利侵害を受けた被害者が、サイト管理者や経由プロバイダに対して、発信者(投稿者)の特定に資する情報(発信者情報)の開示を請求する手続をいいます。
この制度は、プロバイダ責任制限法(正式名称:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)に定められています。
インターネットやスマートフォンの普及により、誰でも気軽に情報発信をすることが可能になりました。その反面、匿名の投稿による誹謗中傷も多く発生しています。
違法な投稿を行った者(投稿者)に対して、被害者は損害賠償等を請求することが可能です。しかし、投稿者の住所や氏名が分からなければ法的な請求を行うことはできません。
そこで、投稿者への法的請求の前段階として、匿名の投稿者を特定するための手段として使われるのが、この発信者情報開示請求の手続です。
発信者情報開示請求の流れ
発信者情報開示請求は、基本的に次の2ステップが必要です。
- ① サイト管理者に対する発信者情報開示請求
- 問題のある投稿が掲載されたサイトの管理者に対し、IPアドレスやタイムスタンプ等の開示を求める
- ② 経由プロバイダに対する発信者情報開示請求
- 投稿時のIPアドレスを割り当てた経由プロバイダ(ISP)に対して契約者の住所や氏名の開示を求める
これらを順番に解説していきます。
なお、2022年に施行された改正法により、発信者情報開示請求が1つの手続で可能になったということが報道されています。これは、上記①②を1つの裁判手続で行うことができるようになったということであって、①②のステップを取ることに変わりはありません。
① サイト管理者に対する発信者情報開示請求
匿名の投稿によって権利侵害を受けた被害者は、まず違法な投稿がなされたサイト(電子掲示板やSNS)の管理者に対して発信者情報開示請求を行います。
サイトの管理者が投稿者の氏名や住所などの情報を保有していることはほとんどありませんので、サイト管理者には、投稿に使用されたIPアドレスや投稿のタイムスタンプの開示を請求することになります。
② 経由プロバイダに対する発信者情報開示請求
サイト管理者からのIPアドレスの取得に成功すると、投稿時のIPアドレスを割り当てた経由プロバイダを調査することができます。
経由プロバイダとは、ユーザーに対してインターネットの接続サービスを提供する事業者を指します。例えば、NTTdocomo、KDDI、ソフトバンクのほか、NTTコミュニケーションズ、JCOMなどがあげられます。
経由プロバイダに対しては、サービス契約者の氏名や住所などの情報の開示を請求します。経由プロバイダからの情報の開示を受けることにより、違法な投稿をした犯人の特定が成功するという流れになります。
投稿者(犯人)特定までの期間は?
発信者情報開示請求を始めてから投稿者を特定するまでには、3か月~6か月程度かかることが一般的です。
サイト管理者や経由プロバイダによって発信者情報開示請求への対応はまちまちですから、その影響で特定までの期間に違いが生じてきます。
また、発信者情報開示請求を受けたサイト管理者や経由プロバイダは、発信者に対して「意見照会」を行う義務があります。発信者がこの意見照会に対して開示に同意すると回答した場合は、結果的に投稿者特定までの期間が短くなります。
発信者情報開示請求の具体的なやり方
発信者情報開示請求のやり方は、大きく分けて以下の2つがあります。
開示請求の方法
- 1 任意請求
- 2 裁判
それぞれについて解説していきます。
1 任意請求
任意請求とは、裁判の手続によらずに行う(発信者情報開示の)請求をいいます。
実務上は、「発信者情報開示請求書」という書面を郵送して行うのが一般的です。発信者情報開示請求書の書式は、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会のHPで公開されています。
郵送で発信者情報開示請求を行える点で任意請求はメリットがありますが、反面、任意請求では開示に応じないとするサイト管理者や経由プロバイダがほとんどです。
この理由は、サイト管理者や経由プロバイダは個人情報保護の義務を負っていることや、簡単に開示してしまっては投稿者からプライバシー権侵害の主張を受ける可能性があることがあげられます。
任意請求が有効に活用される場面もありますが、投稿者(犯人)特定を達成するための現実的な方法とはいいがたいところがあります。
2 裁判
実務上は、発信者情報開示請求を裁判の形で行うことがほとんどです。
裁判所が開示を認めると判断した場合は、サイト管理者や経由プロバイダはその判断に従って情報を開示することになります。
一口に裁判といっても、発信者情報開示請求の関係では更に3つの手続に分けられます。
開示請求の3つの方法
- (1)仮処分
- (2)通常訴訟
- (3)発信者情報開示命令申立
(1) 仮処分
仮処分は、主にサイト管理者に対するIPアドレス等の開示請求のために利用されてきました。
通常訴訟よりも早く審理が終わるという点でメリットがありましたが、担保金を供託しなければならないなどのデメリットもありました。後述の発信者情報開示命令申立の制度ができた現在では、利用される場面は限定的といえます。
(2)通常訴訟
通常訴訟は、経由プロバイダに対してサービス契約者の住所や氏名の開示を請求する際に利用されてきました。
こちらも判決までに数か月かかるというデメリットがあり、発信者情報開示命令申立の制度ができた現在では、利用される場面は多くはありません。
(3)発信者情報開示命令申立
発信者情報開示命令申立は、2022年に新設された裁判手続です。
担保金の供託などは必要なく、また通常訴訟よりも早く決定が出ることがほとんどですので、現在ではこの手続が利用されることが多くなっています。
この制度の最大の特徴は、従来は別々の手続だったサイト管理者への開示請求と経由プロバイダへの開示請求を一括して行うことができる点です。
これにより被害者の手続の負担が減った半面、解釈や運用が定まっていない点もあり、課題がないというわけではありません。
まとめ
以上が発信者情報開示請求の手続の説明です。
当事務所では、発信者情報開示請求の実績が豊富にあります。
発信者情報開示請求についてお困りの方は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。
ネットでした定期購入は解約可能?誤って契約した場合の対処法を弁護士が解説!
インターネットで化粧品やサプリメントを購入したら、実は定期購入の契約だった・・こういったトラブルが後を絶ちません。
・お試し価格でサプリメントを購入したら実は定期購入となっており多額の代金を請求された
・試供品の化粧品を申し込んだら自動的に定期購入の契約にさせられて困っている
・定期購入の契約を解約したいが、電話が一向につながらず解約できない
こういったお悩みを抱えている方が多くいらっしゃいます。
そこで今回は、ネットで誤って定期購入の契約をしてしまったときの対処法を、ネットの法律問題に強い弁護士が解説します。
誤って契約した定期購入は取消しできるケースがある
令和4年に施行された改正特商法(特定商取引に関する法律)により、誤って契約してしまった定期購入を取消しできる範囲が拡大しました。
具体的には、ネット契約の最終確認画面(「購入する」「申し込む」などのボタンがあるページ)が次のような場合に、取消しが認められます。
契約する商品の「総数」の記載がない(又は分かりづらい)
特商法には、契約する商品の総数を最終確認画面に明記しなければならないというルールがあります。
1 販売業者又は役務提供事業者は、当該販売業者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの委託を受けた者が定める様式の書面により顧客が行う通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又は当該販売業者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの委託を受けた者が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により顧客の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続に従つて顧客が行う通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み(以下「特定申込み」と総称する。)を受ける場合には、当該特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面に、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(1)当該売買契約に基づいて販売する商品若しくは特定権利又は当該役務提供契約に基づいて提供する役務の分量
(以下略)
例えば、「お試し3パック無料お届け」との表示がされていても、それが1年間の定期購入で毎月3パック届く場合は、「合計36パックの購入となります」と最終確認画面に表示されていなければいけません。
また、期間を定めない契約(解約するまで継続する契約)であっても、目安として例えば1年間に購入することになる数量は記載されていることが望ましいとされています。
このようなルールに違反し、単に「お試し3パック無料お届け」とだけ表示されている場合、又は注意深く読まないと気が付かない程度にしか表示されていない場合は、契約を取り消すことが可能です。
明確な「販売価格」の記載がない(又は分かりづらい)
特商法には、契約における価格を最終確認画面に明記しなければならないというルールがあります。
1 (略)
(1)(略)
(2)当該売買契約又は当該役務提供契約に係る第11条第1号から第5号までに掲げる事項
(以下略)
1 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
(1)商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
(以下略)
例えば、「今だけ980円!」との表示がされていても、それが定期購入であり、2か月目以降は10,000円であるような場合は、「1回目は980円」「2回目以降は10,000円」と最終確認画面に表示されていなければいけません。
また、仮にそれが1年契約である場合は、「合計11,980円」であることも明記する必要があります。
さらに、期間を定めない契約(解約するまで継続する契約)であっても、目安として例えば1年間の購入代金の合計額は記載されていることが望ましいとされています。
このようなルールに違反し、単に「今だけ980円!」とだけ表示されている場合、又は注意深く読まないと気が付かない程度にしか表示されていない場合は、契約を取り消すことが可能です。
「期間限定」の内容が事実と異なる
ネット通販の場合、契約を促すため期間限定をうたうことがよくあります。
期間が終了するまでの時間をリアルタイムにカウントダウンし、消費者を心理的に焦らすことも多くあります。
しかし、改めてそのページにアクセスするとカウントダウンしたはずの時間が戻っていたり、期間が経過しても同じように商品が販売されていることがあります。
特商法には「期間限定」の内容を最終確認画面に正しく表示しなければならないというルールがあります。
1(略)
(1)~(3)(略)
(4)商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約に係る申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
(以下略)
上記のようなケースは、このルールに違反するものであって、契約を取り消すことが可能です。
解約のルールについて記載がない(又は分かりづらい)
定期購入の契約を解約しようとしても、そこで初めて解約の条件(追加で個人情報を提供しなければならないとか、改めてアプリをインストールして操作しなければならないなど)や違約金の支払いを求められることがあります。
また、解約専用ダイヤルの電話番号があるものの、その電話番号にはいつかけても一向につながらないというケースもあります。
特商法には解約の条件を最終確認画面に正しく表示しなければならないというルールがあります。
1(略)
(1)~(4)(略)
(5)商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第二十六条第二項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)
(以下略)
また、解約方法として電話によることを表示している場合は、確実につながる電話番号の表示が求められています。
上記のようなケースは、これらのルールに違反するものであって、契約を取り消すことが可能です。
その他取消しができるケース
上記のほかにも、以下のような場合には定期購入の契約を取り消すことができます
・最終確認画面に代金の「支払い時期」が明記されていない
・最終確認画面に商品の「引き渡し時期」が明記されていない
・契約成立のボタンであるにもかかわらず「送信する」「次へ」としか表示されていなかった
・実際は商品の購入であるにもかかわらず、「お試し」や「トライアル」という表現が強調されている
・実際は解約の条件があるにもかかわらず「いつでも解約可能!」という表現が強調されている など
定期購入の解約・取消しを実現する効果的な方法
まずは販売事業者の連絡先に連絡してみましょう。
連絡がつけば、契約を解約ないし取り消したい旨の意思を伝えましょう。
ただ問題なのは連絡先が明記されていないとか、連絡は付いたが解約に応じてくれない場合です。
このような場合は、販売事業者宛てに内容証明郵便を送付することが効果的です。
特に取消しは一方的な意思表示ですので、内容証明郵便でその意思が相手に伝わったことが記録として残れば、法律上はそれで取消しが成立します。
警察や自治体、消費生活センターへの相談は有効か
思いがけない定期購入の契約は詐欺のように感じられることもあります。そのため、警察や自治体、消費者生活センターへの相談をご検討の方も多いと思います。
もちろん、それらの機関も相談には乗ってくれますが、民事的なトラブルに直接介入したり、相談者の代理人としてトラブル解決にあたる権限があるわけではありません。
なお、(ケースにもよりますが)思いがけない定期購入の事例で「詐欺罪」が適用されるケースは少ないでしょう。そのため、警察に相談したとても、捜査を開始し逮捕などをしてくれる可能性はかなり低いといえます。
解約・取消しを弁護士に依頼することはできるか
誤って契約してしまったネットでの定期購入の解約・取消しを弁護士が代行することは可能です。
当事務所では、5,500円(税込み)~でネットの定期購入の解約・取消しの意思表示を代行いたします。
この記事でご説明した以外でも定期購入の解約・取消しができるケースもありますので、ネット定期購入の解約でお困りの方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
Vtuberにも認められる開示請求|成功のポイントや過去の裁判例について解説
近年、Vtuberの人気が高まっており、市場規模も年々拡大しているようです。
しかし、注目が集まると同時に問題となっているのが、Vtuberに対する誹謗中傷です。Vtuberへの誹謗中傷について開示請求が認められたという報道も目にすることがあります。
そこで今回の記事では、Vtuberの方による開示請求について、成功のポイントや過去の裁判例のまとめなどを紹介します。
この記事はこんな方におすすめ
・誹謗中傷を受けているVtuberの方
・Vtuberによる開示請求の成功のポイントが知りたい方
・Vtuberに関する過去の裁判例を知りたい方
Vtuberとは
Vtuberとは、過去の裁判例では2D又は3Dのバーチャルキャラクターを用いて動画配信等を行うYouTuberであり、声優等とは異なり、個人が当該キャラクターを操作することを前提とするものと定義されています(東京地判令和 4・7・1)。
外見上はバーチャルのキャラクターですが、Vtuberは演者(いわゆる「中の人」)として声を当てるほか、モーションキャプチャーの技術を使ってリアルタイムに表情や動きを読み取り、それをキャラクターの表情や動きに反映します。
活動内容は主にインターネットでのライブ配信や動画投稿ですが、歌手として楽曲をリリースしたり、最近ではCMに出演することも珍しくありません。
Vtuberはそのキャラクターを演じるというよりは、演者自身の活動を、バーチャルキャラクターというフィルターを通して提供しているという要素が強いといえます。
バーチャルキャラクターそのものの設定(アトランティスの末裔とか、海賊団の船長など)もありますが、ライブ配信における「雑談」やSNS上の投稿においては、演者自身の実際の経験(実際に食べたものや訪れた場所など)が話されることがほとんどです。
Vtuberが誹謗中傷の被害を受けやすい理由
Vtuberが誹謗中傷を受けやすい理由は様々考えられますが、代表的なものは以下の2点があると考えられます。
「中の人」の素性が公開されていない
Vtuberは、自身の素性を公開していないことが一般的です。
容姿や年齢、出身地などは明らかにされていないため、かえってそれらを知りたいという欲求が刺激される人も多くいることでしょう。
そのためか、憶測やリーク情報(らしきもの)によるプライベートの情報が投稿されることも多くあります。
また、中には他の名義で活動している人を、Vtuberの「前世」(過去の名義)として結び付け、「前世で●●と言っていた(公開していた)からこのVtuberは●●だ」などと投稿されることもあります。
Vtuberの素性が公開されていない以上、(褒められたことではありませんが)プライベートの情報が注目を集め、結果としてプライバシー権侵害が生じてしまうことがあります。
過激な発言による誹謗中傷の誘発
Vtuberの活動の中では過激な発言や性的(と受け取られるよう)な発言がなされることもあります。
過激な発言そのものが非難の対象になることもあります。
しかし、より多いのが「過激な発言や性的な発言をしている人だから、このくらい言っても大丈夫だろう」と誤解し、行き過ぎた誹謗中傷を投稿してしまうというものです。
もちろん、Vtuberとしてはエンターテイメントとして過激な発言をしているものです。その意味で、Vtuber側に落ち度があるわけではありませんが、それを誤った方向で受け取る人もおり、その結果誹謗中傷の誘発につながっているということがあります。
どのような投稿が開示請求の対象になるか
開示請求は、あくまで法的に権利侵害があることが必要です。単に「配信がつまらなかった」とか「ゲームが下手だった」というだけでは単なる意見・感想ですから、こういった投稿が権利侵害が認められる可能性は低いといえます。
一方、Vtuberに対する誹謗中傷の内容はある程度パターンがあり、権利侵害が認められるものもある程度決まっています。代表的なものは、以下が該当します。
Vtuberの権利侵害が認められる誹謗中傷の典型例
・知的障害や精神疾患に該当するとの指摘
・年齢の公開
・家族や交際相手についての指摘
・住んでいる場所に関する情報
・犯罪予告 など
また、Vtuberに対する誹謗中傷が掲載されるサイトもある程度決まっています。典型的には以下のようなサイトですが、そのほとんどが開示請求の対象とすることができます。
Vtuberに対する誹謗中傷が掲載されるサイトの例
・5ちゃんねる(5ch.net)
・好き嫌い.com
・X(旧Twitter)
・まとめサイト、トレンドサイト など
>>「好き嫌い.com」の誹謗中傷対策については以下の記事でも解説しています。

誹謗中傷対策としての開示請求のメリット
誹謗中傷対策としての開示請求のメリットは、次のものがあります。
- 投稿者本人に削除を請求できる
- 将来の投稿をしないよう誓約させることができる
- 損害賠償を請求することができる
① 投稿者本人に削除を請求できる
削除請求は、投稿が掲載されたサイト管理者やサーバの管理者に対して行うことが一般的です。
もっとも、投稿者自身が削除できる投稿(SNSのコメントなど)については、投稿者を特定して本人に削除請求を行った方が確実な場合もあります。
② 将来の投稿をしないよう誓約させることができる
誹謗中傷の投稿が削除できたとしても、同じ投稿者が同じような投稿を繰り返す場合は誹謗中傷対策として十分とはいえません。
このような場合は、投稿者を特定して、二度と投稿しないという誓約をさせることが効果的です。
開示請求を行うことは、「行き過ぎた行為には法的措置をとる」という態度を(投稿者以外にも)示すことができるため、将来の誹謗中傷を抑止するという効果も期待できます。
③ 損害賠償を請求することができる
損害賠償にあたっては、⑴慰謝料と⑵調査費用(特定にかかった弁護士費用)を請求することが一般的です。
損害賠償が数百万円に及ぶことはまれですが、それでも金銭的な負担を負わせることは投稿者にとって非常に大きいペナルティとなります。
投稿者特定後は示談で終わることが多いですが、示談交渉が決裂した場合は裁判手続に移行することも可能です。
開示請求を成功させるポイント
Vtuberの方も開示請求ができるといっても、Vtuberの案件特有の難しさがあります。開示請求を成功させるポイントとしては、以下の点があげられます。
特定性(同定可能性)の証明
Vtuberはその素性を公開してはいないことが一般的です。そのため、誹謗中傷で名指しされるのはバーチャルキャラクターの名義であって、実際の演者の名前ではありません。
しかし、「権利が侵害された」と言えるのは実在の「人」であって、キャラクター自体の権利侵害は認められていません。そうすると、バーチャルキャラクターに対する誹謗中傷が、演者本人の権利を侵害するか、という点が問題になります。
この点について適切に証明することが、法的対策を成功させるポイントなります。
投稿内容の意味内容の適切な理解
Vtuberに関する話題においては、専門用語やインターネットスラングが飛び交うことがほとんどです。
また、Vtuberの事務所名や他のVtuberの名前なども当然のように話題にあがるので、一見すると何を言っているか分からないというケースも珍しくありません。
そして、開示請求を行う際は、権利侵害の理由を適切に説明する必要があります。そのため、前後の文脈も含めてその投稿がどういう内容を意味し、どういう点で権利侵害があるのかということを適切に説明することが成功のポイントになります。
(投稿者特定の場合)迅速な対応
開示請求において、経由プロバイダのログ保存期間が問題になります。
投稿日から時間が経過したものについては、このログ保存期間の関係で投稿者特定が実現しない可能性が高くなります。
また、開示請求の手続を迅速に行わないと、手続きに手間取ってログ保存期間が経過してしまうというリスクもあります。
そのため、開示請求においては手続に精通している専門家による迅速な対応が不可欠です。
>>プロバイダのログ保存期間については、以下の記事でも解説しています。

「身バレ」を防いで開示請求を行うことはできるか
この点については、2023年に創設された「住所、氏名等の秘匿制度」により、一定の要件の下に自身の情報を公開せずに開示請求の裁判を行うことができるようになりました。
この制度を利用することで、裁判の傍聴、記録閲覧、発信者への意見照会など各種手続きでも開示請求者の情報は公開されないことになります。
Vtuberの方が開示請求を行ううえで懸念されるのがいわゆる「身バレ」ですが、この制度を利用により法的措置に踏み切るハードルは低下したといえます。
実際、当事務所でも「住所、氏名等の秘匿制度」を利用した開示請求の実績が多くあります。
Vtuberに関する過去の開示請求の裁判例
これまでのVtuberに対する権利侵害が問題となった裁判例について紹介します。
(※プライバシー権保護の観点から、具体的な事実については抽象化しています。)
年齢に関する投稿でプライバシー権侵害が認められた事例(東京地判令和2・12・22)
Vtuberの「概ねの年齢」を「5ちゃんねる」に投稿したことで、開示請求が認められた事例です。年齢についての投稿がプライバシー権侵害に該当すると認定されました。
なお、過去にそのVtuberがテレビ番組に出演したことがあり、その際に個人情報が表示されたことがあったようですが、それは投稿日より10年も前の出来事であるとして、プライバシー権侵害の成立は否定されないと判断されています。
生育環境に結び付けた批判で名誉感情侵害が認められた事例(東京地判令和3・4・26)
「5ちゃんねる」に投稿された、Vtuberの生育環境に結び付けた形での批判について、開示請求が認められた事例です。このような批判は、単なるマナー違反等を批判する内容とは異なり、社会通念上許される限度を超えるものとして、名誉感情の侵害が認められました。
ちなみにこのケースでは、特定性(同定可能性)の問題についても言及されました。以下が、特定性の認定に当たって考慮された事情です。
- そのVtuberの名義で活動しているのは原告のみであること
- プロダクションがVtuberのキャラクターを製作する際には、タレントとの間で協議を行った上で、当該タレントの個性を活かすキャラクターを製作していること
- 動画配信における音声は原告の肉声であること
- CGキャラクターの動きについてもモーションキャプチャーによる原告の動きを反映したものであること
- 動画配信やSNS上での発信は、キャラクターとしての設定を踏まえた架空の内容ではなく、キャラクターを演じている人間の現実の生活における出来事等を内容とするものであること
以上の各事情から、そのVtuberの活動は、単なるCGキャラクターではなく、原告の人格を反映したものであると判断されています。
ある人物の顔写真をVtuberの演者の顔であるとして公開したことにつきプライバシー権侵害が認められた事例(東京地判令和3・6・8)
「5ちゃんねる」において、ある人物の顔写真をVtuberの演者の顔であるとして公開したものについて、開示請求が認められた事例です。そのような顔写真の公開はプライバシー権侵害に該当すると判断されました。
年齢を公開したり精神障害に該当するとの投稿で、名誉毀損、名誉感情侵害、プライバシー権侵害が認められた事例(東京地判令和3・12・17)
Vtuberの年齢に関する投稿や、精神障害に該当するとの侮辱的な投稿について、開示請求が認められた事例です。このケースでは、名誉感情侵害やプライバシー権侵害のほか、Vtuberに対する名誉毀損が認められています。
精神的に不調を公表したことについて、それを揶揄するような投稿に対して名誉感情侵害が認められた事例(東京地判令和4・7・1)
精神的な不調により活動を休止していたVtuberについて、それを揶揄するような内容を「Twitter」(現在は「X(エックス」)に投稿したことが名誉感情侵害にあたるとして、開示請求が認められた事例です。
Vtuberのマネジメント会社が、Vtuberのイラストの無断転載について著作権侵害を主張した事例(東京地判令和5・9・25)
Vtuberのイラストを無断でサイトに転載したことについて、Vtuberのマネジメント会社が、そのサイトのサーバーを管理する会社に対して開示請求を行った事例です。このケースでは、イラスト転載の際に一部が切り取られていたようですが、それでも著作権侵害は認められました。
マネジメント会社がイラストレーターから著作権を譲り受けていたことから、マネジメント会社を原告として訴えを提起することができた事例です。このように、主張する権利の種類によっては、Vtuber本人でなくマネジメント会社が原告となることもあります。
まとめ
Vtuberに対する誹謗中傷の問題は比較的新しい分野ですが、従来の誹謗中傷問題と共通するところもあり、対策が可能なケースも多くあります。
当事務所では、Vtuberの誹謗中傷問題を取り扱っております。
Vtuberに対する誹謗中傷問題でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
トレント(torrent)の発信者情報開示請求 よくある質問について専門弁護士が解説
トレント(torrent)の使用で開示請求を受け、プロバイダから意見照会書が届いたというご相談をいただく機会が多くなっています。
ご相談者の方から受けるご質問については、共通する内容も多くあります(皆さま疑問やご不安に思われる点は同じということです)。
そこで今回は、トレント(torrent)の開示請求について、よくある質問を弁護士が解説します。
※2024年9月23日更新
- Q プロバイダから意見照会書が届いたときは必ず開示されますか
- Q 非開示を目指すべきケースはどのようなものですか
- Q 開示に同意したくないのですが拒否の理由には何を書けばよいですか
- Q 開示に同意して示談を選択すべきケースはどのようなものですか
- Q 示談金の相場はいくらくらいですか
- Q 開示請求が複数届くことはありますか
- Q 追加の開示請求が届くのはいつまでですか
- Q 示談金を支払うことでかえって開示請求を受けやすくなるということはありますか
- Q トレント(torrent)の使用で逮捕されることはありますか
- Q 意見照会書を送ってきたプロバイダを解約してもよいですか
- Q 開示請求を受けていますが、引越しをしても大丈夫でしょうか
- Q 個人で楽しむ目的のダウンロードでも開示されますか
- Q トレントの仕組みはどういうものですか
Q プロバイダから意見照会書が届いたときは必ず開示されますか
トレント(torrent)の使用について意見照会を受けた場合であっても、必ず個人情報が開示されるとは限りません。
ただし、過去の裁判例を見ると、裁判所が非開示の判断をするのは「IPアドレス等の取得過程の正確性に疑義があるケース」がほとんどです。そして、現実的にはこのような反論を十分行うことができるケースは限定的であり、基本的には裁判所は開示を認めることが一般的です。
そのため、現実的には開示されるケースの方が多い状況です。
Q 非開示を目指すべきケースはどのようなものですか
開示請求の要件である「権利侵害の明白性」に疑義があるケースでは、非開示を目指すべきであるといえます。
例えば、著作権侵害を根拠に開示請求がされているが、開示請求者はその作品の著作権を保有していないといえるような場合です。
また、開示請求者側が行ったIPアドレス等の取得の正確性に疑義がある場合で、その点を的確に反論できるケースも、非開示を目指すべきといえます。
ただし、システムを利用してIPアドレス等の取得が行われていることもあります。この場合は、システムの要件や仕様を正確に把握したうえで、技術的な側面から反論する必要がありますから、現実的には困難なケースがほとんどいえるでしょう。
Q 開示に同意したくないのですが拒否の理由には何を書けばよいですか
その発信者情報開示請求が、法律の要件を満たしていないという法的な反論を記載する必要があります。
拒否の理由については、以下の記事で詳しく解説しています。

Q 開示に同意して示談を選択すべきケースはどのようなものですか
開示の可能性が高いと見込まれるケースや、早期の示談成立を希望するケース、同居のご家族や職場に知られたくないようなケースでは、開示に同意したうえでの示談を選択するのが妥当でしょう。
また、示談をすることで刑事告訴の可能性をなくしたいという場合も示談をすべきといえます。
なお、開示の可能性が高いと見込まれるケースの場合、プロバイダに対して開示に「同意しない」という回答をしても時間稼ぎにしかならず、最終的なトラブル解決までの期間が延びてしまうことがデメリットとして考えられます。
Q 示談金の相場はいくらくらいですか
示談交渉において、著作権者側から提示される示談金の相場は、1作品あたり30~70万円です。
また、「包括示談」のオプションを提示されることもあります。この場合の相場は70~80万円です。
示談金の相場や示談の流れ等については、以下の記事で詳しく解説しています。

Q 開示請求が複数届くことはありますか
複数回の開示請求を受け、プロバイダからの意見照会書が2件目、3件目・・・と届くというケースも珍しくありません。
この理由は、著作権者側(開示請求者側)の事情が関連しています。
著作権者側はトレントを監視しIPアドレス等を取得していますが、その手段によっては得られるIPアドレス等の件数は非常に多くなることがありますし、また随時取得されていきますから、一度にすべての開示請求を行うことは現実的ではありません。そのため、著作権者側としては何度も開示請求を行うことになります。
このような事情で、トレント(torrent)使用者のところにプロバイダからの意見照会書が複数回にわたって届くことがあります。意見照会書を受け取る側としては、嫌がらせであるとか、何か意図があって何度も開示請求を行っているのではないかと疑ってしまうこともあるでしょう。しかし、その可能性は低いと考えます。
Q 追加の開示請求が届くのはいつまでですか
トレント(torrent)の使用をやめてから何か月後、という明確な期間を提示することはできません。ただ、各プロバイダのログ保存期間が影響することは間違いありません。
各プロバイダにはログ保存期間というものがあり、それを経過するとプロバイダはIPアドレス等から契約者を特定できなくなります。契約者を特定できないと、意見照会書を送ることもできません。
そのため、少なくともトレント(torrent)の使用をやめてから契約しているプロバイダのログ保存期間が経過するまでは、開示請求が届く可能性があります。
ただし、著作権者側もプロバイダに対して一定期間のログの保存の要請をすることができます。また、開示請求がされてから意見照会書が届くまで数ヶ月のタイムラグがあることもあります。
そのため、ログ保存期間が経過したからといって直ちに開示請求が来なくなるというわけではありません。個人的には、ログ保存期間が経過してから半年程度は開示請求が届く可能性があると考えたほうが良いと思います。
最近では、1年半~2年前の通信記録についての開示請求が届いたというご相談を多くいただいております。この理由としては、プロバイダが大量の開示請求を受けており処理が追い付いていない等の理由が考えられます。
Q 示談金を支払うことでかえって開示請求を受けやすくなるということはありますか
示談金を支払ってしまったためにかえって連続して開示請求を受ける、という可能性は低いと考えます。
この疑問はおそらく、示談金を支払ったという事実が(同業者間で)拡散・共有されたりするのではないか、という懸念があるためだと考えられます。しかし、示談金を支払ったという事実を(同業者間で)拡散・共有するという行為は、プロバイダ責任制限法7条に反するものです。
また、同じIPアドレスであっても、通信時間が異なれば割り当てられた契約者も異なることが一般的です。そのため、著作権者側においても、特定の契約者のみを狙い撃ちすることは現実的ではありません。
Q トレント(torrent)の使用で逮捕されることはありますか
逮捕される可能性はあります。詳しくは以下の記事で説明しています。
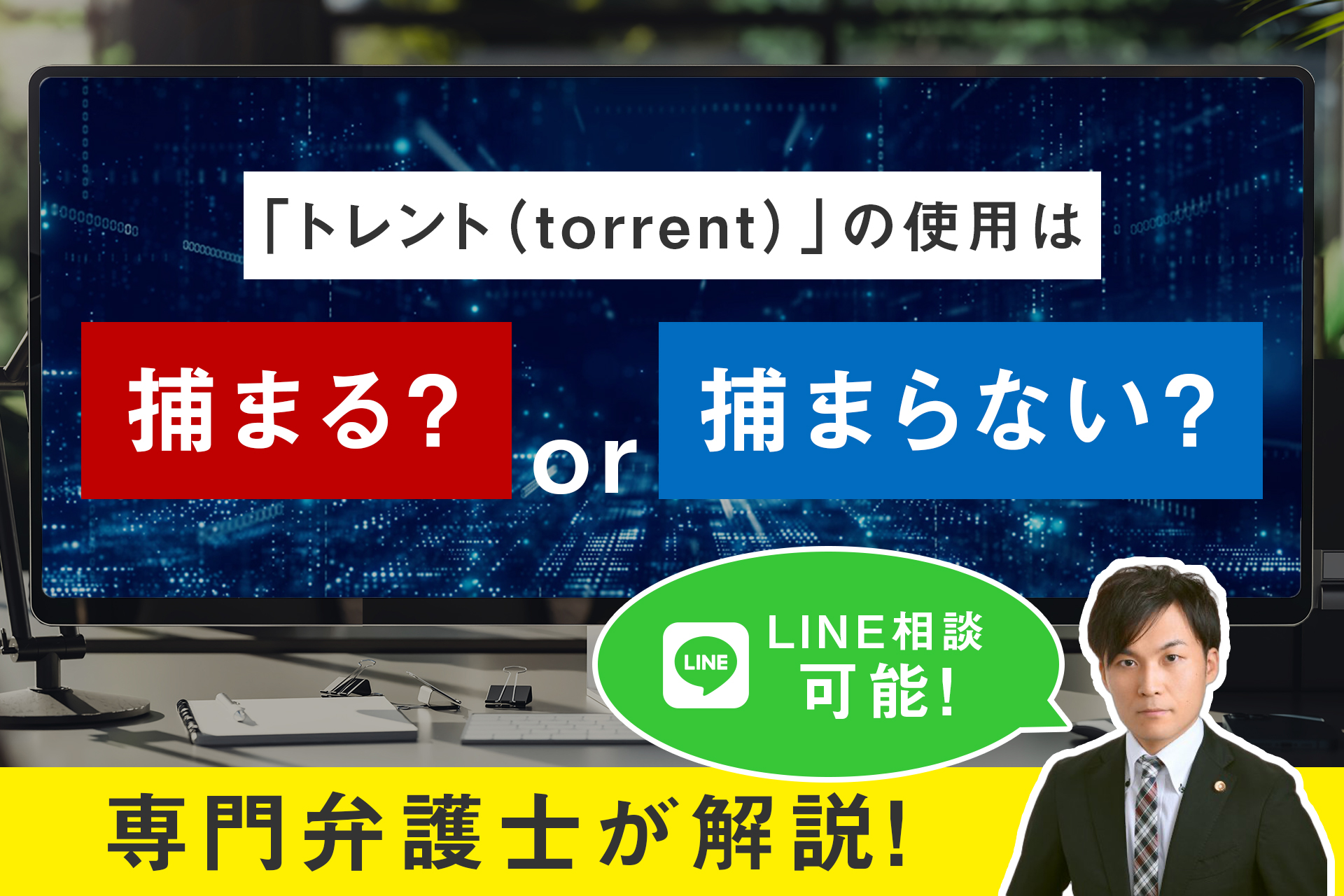
Q 意見照会書を送ってきたプロバイダを解約してもよいですか
意見照会書が届いた後であれば、プロバイダを解約しても開示手続に影響はありません。
そのため、解約したからといって何らかのペナルティが発生することはありませんが、一方で、解約したからといって開示を免れるわけではありません。
Q 開示請求を受けていますが、引越しをしても大丈夫でしょうか
ご自宅を転居されても、開示請求に影響はありません。また、転居自体にペナルティなどはなく、相手方や裁判所の心証を害するということも基本的にはありません。
なお、転居の有無や転居先は弁護士が調査可能なことが一般的ですから、転居したために法的責任の追及を免れるということはありません。
Q 個人で楽しむ目的のダウンロードでも開示されますか
トレント(torrent)においては、ダウンロードが完全に終了していないユーザー(リーチャー)であっても、ダウンロード済みのデータ(ピース)を同時にアップロードするという仕組みになっています。
つまり、アップロードの責任も問われることになるため、仮にダウンロードに問題がなかったとしても、違法アップロードを行った者として開示は認められることになります。
なお、個人で楽しむ目的(私的使用目的の)ダウンロードについても、それが違法ダウンロードに該当する場合は著作権侵害の責任を負うことになります。
違法ダウンロードについて詳しくは下記の記事で解説しています。

Q トレントの仕組みはどういうものですか
トレントの仕組みは過去の裁判例で簡潔に説明されていますので、それをベースにファイル共有の流れを解説します。(東京地判令和5年10月30日の判示部分より)
- ビットトレント(BitTorrent)を利用したファイル共有は、その特定のファイルに係るデータをピースに細分化した上で、ピア(ビットトレントネットワークに参加している端末)同士の間でピースを転送又は交換することによって実現されます。
- 上記ピアのIPアドレス及びポート番号などは、「トラッカー」と呼ばれるサーバーによって保有されています。
- 共有される特定のファイルに対応して作成される「トレントファイル」には、トラッカーのIPアドレスや当該特定のファイルを構成する全てのピースに係る情報などが記載されています。
- そして、一つのトレントファイルを共有するピアによって、一つのビットトレントネットワークが形成されます。
- ビットトレントを利用して特定のファイルをダウンロードしようとする利用者は、インターネット上のウェブサーバー等において提供されている当該特定のファイルに対応するトレントファイルを取得することが一般的です。
- 端末にインストールしたクライアントソフトウェアに当該トレントファイルを読み込ませると、当該端末はビットトレントネットワークにピアとして参加し、定期的にトラッカーにアクセスして、自身のIPアドレス及びポート番号等の情報を提供するとともに、他のピアのIPアドレス及びポート番号等の情報のリストを取得します。
- 上記の手順でピアとなった端末は、トラッカーから提供された他のピアに関する情報に基づき、他のピアとの間で通信を行い、当該他のピアに対して当該他のピアが保有するピースの送信を要求し、当該ピースの転送を受けます(ダウンロード)。
- また、上記の端末(ピア)は、他のピアから、自身が保有するピースの転送を求められた場合には、当該ピースを当該他のピアに転送します(アップロード)。
- このように、ビットトレントネットワークを形成しているピアは、必要なピースを転送又は交換し合うことで、最終的に共有される特定のファイルを構成する全てのピースを取得することとなります。
>>トレントの使用者が特定される仕組みについては以下の記事で解説しています。
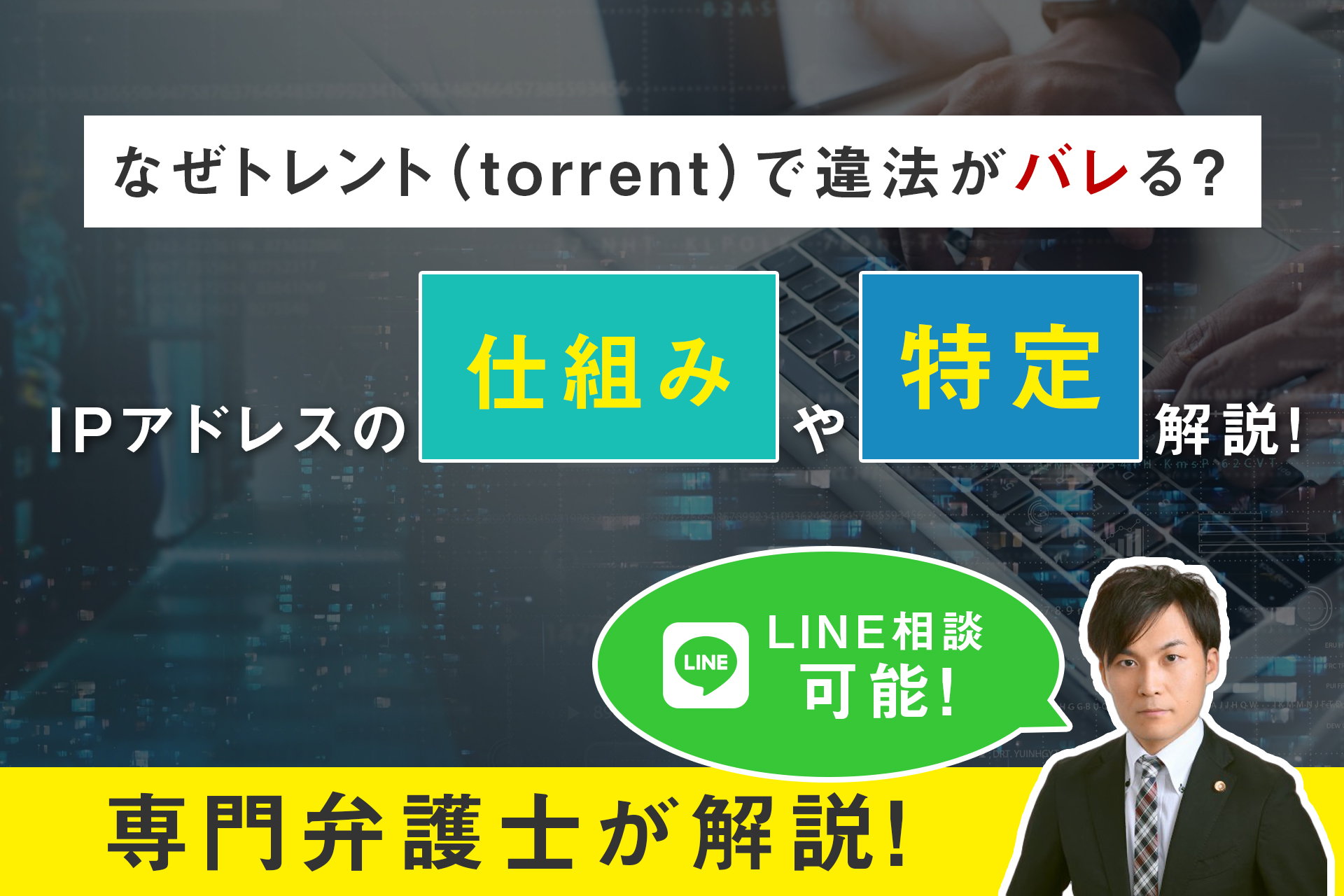
トレント(torrent)の発信者情報開示請求は拒否できる?不同意の理由について解説
トレント(torrent)での開示請求を受けた方から、開示を拒否(不同意)したいという相談を多くいただいております。
・不同意の理由に何を書けばよいか分からない方
・自分で書いてみたが本当に有効か不安な方
この記事では、トレント(torrent)の開示請求は拒否できるのか、また拒否する際の不同意の理由についても解説しています。

開示請求に拒否(不同意)の回答をすれば開示は免れるか
トレント(torrent)の使用について開示請求を受けた場合、プロバイダから意見照会書というものが郵送されます。
この意見照会書には、開示に同意するか拒否(不同意)するか、拒否するのであれば不同意の理由も併せて回答するよう記載されていますから、開示を拒否する(不同意)と回答することもできます。
もっとも、拒否の回答をしても、必ずしも開示を免れるわけではありません。
発信者側(トレント(torrent)使用者側)が開示に同意しなかった場合は、法律上開示が認められるかどうかが判断され、その結果によって開示・非開示が決まります。
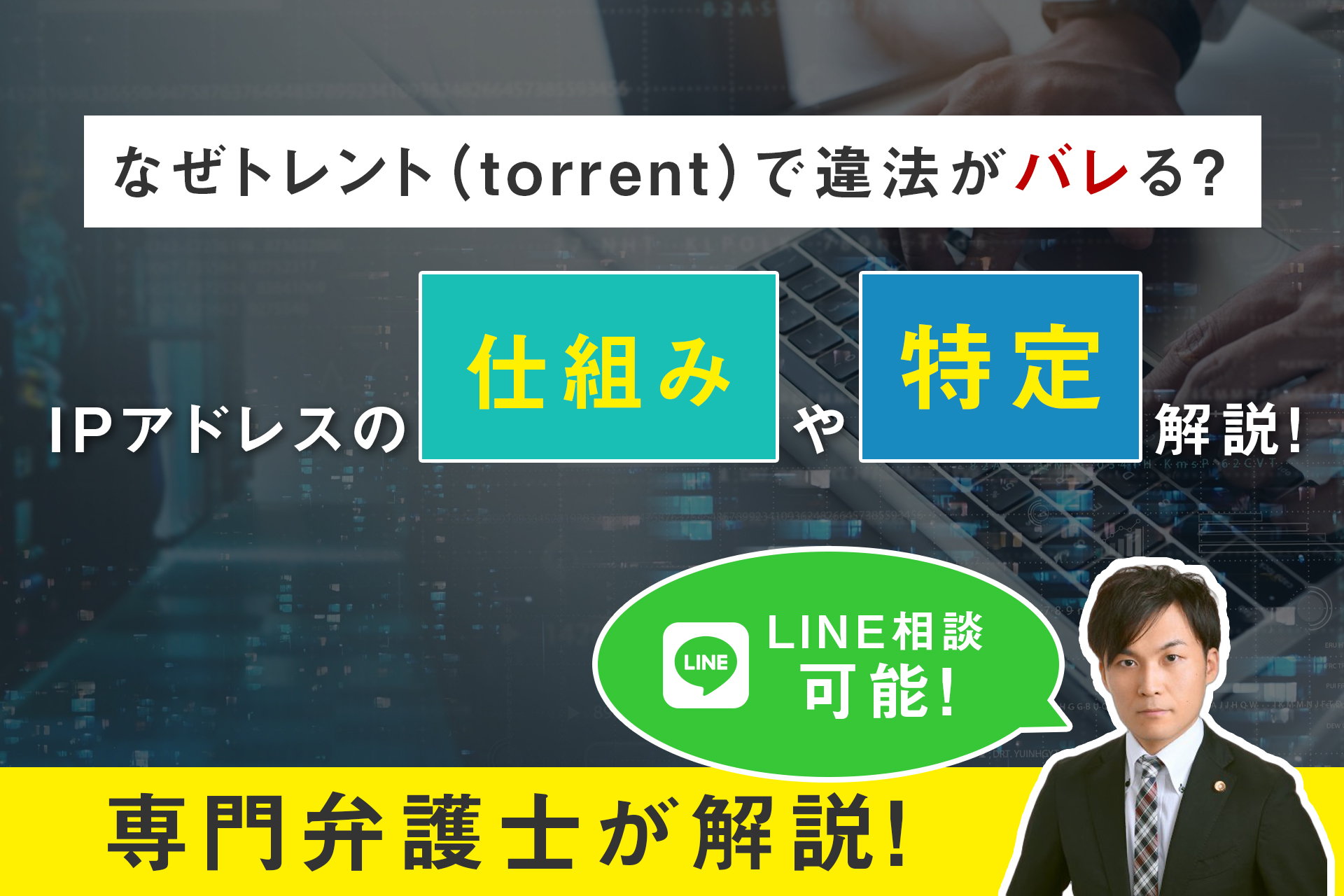
開示請求の拒否(不同意)の理由には何を書けばよいか
拒否(不同意)の理由には、その開示請求が法律の要件を満たしていないという法的な反論を記載する必要があります。
そのため、あくまで法的に有効であることが求められます。以下では、法的な反論として有効なものと、(少なくとも開示請求との関係では)有効にはならないものを説明します。
拒否(不同意)の理由として有効なもの
権利侵害(著作権侵害)の明白性が認められないこと
開示請求が認められるためには、法律上「権利侵害の明白性」が認められる必要があります。
そのため、今回の開示請求が権利侵害(著作権侵害)の明白性を満たさないということは、法的に有効な反論になります。
例えば、ある作品のファイル共有行為について開示請求がなされたが、その開示請求者は当該作品の権利者でないという場合は、「権利侵害の明白性」は認められないことになります。
IPアドレス等の取得の正確性に疑義があること
プロバイダに対する開示請求は、それに先行してトレント(torrent)の使用者のIPアドレスやタイムスタンプ等を取得するという作業が行われています。
これによって得られたIPアドレス等をもとにプロバイダに開示請求をするわけですが、このIPアドレス等の取得方法は開示請求者によって実は違っています。そして、中には取得方法が適切なものでなかったり、正確性に疑問があるものもあります。
適切な方法で得られたIPアドレス等でなければ、それに紐づいた回線契約者の情報は開示の対象とはなりませんから、このような事情は法的に有効な反論となります。
ただし、システムを利用してIPアドレス等の取得が行われていることもあります。この場合は、システムの要件や仕様を正確に把握したうえで、技術的な側面から反論する必要があります。
拒否(不同意)の理由として有効でないもの
トレント(torrent)の使用に身に覚えがない
そもそもトレント(torrent)の使用に身に覚えがないというケースもありますが、単にこの事情だけでは開示を拒否する理由としては法律上有効とはなりません。
先述のとおり、開示請求者側はプロバイダに対する開示請求に先行して、トレント(torrent)の使用者のIPアドレスやタイムスタンプ等を取得しています。
これによって得られたIPアドレスやタイムスタンプ等に紐づいた回線契約者の情報は、その取得が適切なものである限り開示の対象となります。
つまり、回線契約者がトレント(torrent)の使用者でないという事実は、法律上は開示を妨げる事情にはなりません。回線契約者が使用者でなくても、同居の家族が使用している場合などもあるからです。
法律がこのような建付けになっているため、仮に回線やデバイスが乗っ取られたケースであっても、乗っ取りの被害者の情報が開示されることになります。
ダウンロードしたファイルに身に覚えがない
トレント(torrent)の使用はしていたが、ダウンロードしたとされるファイルに身に覚えがないケースもありますが、この事情も開示を拒否する理由として法律上は有効とはなりません。
上記のとおり、開示請求者側がトレント(torrent)に使用されたものとして取得したIPアドレスやタイムスタンプ等に紐づいた回線契約者の情報は、その取得が適切なものである限り開示の対象となります。
そのため、単にファイルに見覚えがないとか、ダウンロードした記憶がないというだけでは有効な反論とはなりません。
ダウンロードしたファイルの正規品を後から買った
違法なダウンロードをした後に正規品を購入し、正規の金額を支払ったとしても、過去の違法がなくなるわけではありません。
仮に後から買えばよいというルールになっていると、「違法を指摘されたら買えばよい」ということになってしまい、違法ダウンロードを助長してしまうからです。
また、トレント(torrent)はダウンロードをしていると同時にアップロードもするという仕様となっています。そのため、法的な責任としては1本のダウンロードだけではなく、アップロードについても責任を問われるものです。
したがって、違法にダウンロードしたファイルの正規品を後から買ったというのは開示を拒否する理由としては法律上有効とはなりません。
示談金を払うから開示はしてほしくない(匿名で示談したい)
示談金を払うから開示してほしくないというのは、法律上有効な反論ではありません。
開示請求者の中には、匿名での示談に応じ、示談金の支払いが確認出来たら開示請求は取り下げるという対応をする者もいます。
しかしそれは、あくまで開示請求者側が任意に匿名での示談に応じているだけで、そのような示談が拒否されればそれまでです。
示談金ビジネスであり不当な請求だ
トレント(torrent)の開示請求に関して、しばしば「示談金ビジネスだ」とか「不当な請求だ」いう批判的意見を目にします。
しかし、開示請求者側も違法なアップロード・ダウンロードという被害を被っていることはあります。そのため、単に不当な示談金要求の開示請求だという批判は、少なくとも開示請求の反論としては成立しません。
>>トレントに関するよくある質問についてはこちらでも解説しています。

「好き嫌い.com」の投稿者は特定可能?「好き嫌い.com」の誹謗中傷問題を徹底解説!
近年、「好き嫌い.com」というサイトにおける誹謗中傷問題について、ご相談を多くいただいております。
「好き嫌い.com」における誹謗中傷は実際少なくありません。
そして、損害賠償など法律問題になっているケースも多くあります。
そこで今回は、「好き嫌い.com」の誹謗中傷問題について解説したいと思います。
「好き嫌い.com」はどういうサイトか
「好き嫌い.com」は、主に人を話題の対象にするスレッドで成り立っています。
話題の対象となる人は、著名人やタレントの方、政治家、YouTuberやVtuberなどです。
そのスレッドを閲覧しに行くと、まず、その対象の人が「好き」か「嫌い」かを投票するページが表示されます。
「好き」か「嫌い」か、どちらか投票すると、今度は他のユーザーが投稿したコメントが見られるページになります。
また、ここでは自分からコメントを投稿することもできます。
コメントを投稿する際は、自分が「好き派」なのか「嫌い派」なのかを選択することになります。
このサイトでは、特に「嫌い派」からのコメントができるため、ネガティブな内容のコメントが投稿されやすい傾向があるといえます。
単にその人が「好みでない」とか「考え方が合わない」という意見・感想なら問題は生じにくいでしょうが、それを超えて誹謗中傷が投稿されることも多くあり、これが法的なトラブルに発展する可能性が高いものになります。
>>Vtuberに対する誹謗中傷問題についてはこちらの記事で解説しています。
「好き嫌い.com」で誹謗中傷を受けたときの対処法
「好き嫌い.com」で違法な誹謗中傷を受けたときは、法的措置として次の対策が可能です。
誹謗中傷に対して有効な法的措置
- 削除請求
- 投稿者(犯人)特定(開示請求)
このうち、②の投稿者(犯人)特定(開示請求)が成功した場合は、さらに投稿者に対して損害賠償請求などを行うことができます。
「好き嫌い.com」で投稿者(犯人)特定は可能か
「好き嫌い.com」では、サイト管理者が公開されていないために開示請求ができないと考える方もいらっしゃいます。
しかし、「好き嫌い.com」でも他のサイトと同じように投稿者(犯人)が特定されることがありますし、投稿者(犯人)特定後に被害者から損害賠償請求などがなされるケースも実際に存在します。
「好き嫌い.com」で投稿者(犯人)を特定するには
投稿者(犯人)を特定するためには、発信者情報開示請求という法律の手続が必要です。
投稿者(犯人)特定に至るためには、次の各ステップが必要です。
この2つのステップになります。
どのような投稿が特定の対象となるか
投稿者(犯人)特定が可能であるといっても、あらゆる投稿が開示の対象になるわけではありません。
投稿者(犯人)特定の可能性があるのは、投稿の内容が法的に違法と評価されるときです。
違法と評価されるのは、投稿内容が次に該当するような場合です。
「好き嫌い.com」では、特に「嫌い派」からのコメントがあるため、ネガティブな意見・感想が行き過ぎてしまい、これが違法と評価されることが多くあります。
例えば、顔・容姿について誹謗中傷するものや、精神障害があるかのような指摘をするものは違法と評価される可能性は高いといえます。
Webに関わる法律であればお気軽にご相談ください
「好き嫌い.com」での誹謗中傷問題は、犯人特定などの法律問題に発展する可能性が比較的高いといえます。
当事務所では、「好き嫌い.com」の誹謗中傷問題について取り扱っています。
「好き嫌い.com」に関してお困りのことがあれば、ぜひ一度当事務所までお気軽にご相談ください。
トレント(torrent)で違法になるケースを弁護士が解説
2023年3月に俳優の東出昌大さん主演による映画「Winny」が公開され、大きな反響を呼びました。Winny(ウィニー)と同じくファイル共有ソフトとして有名なのがトレント(torrent)です。
ファイル共有ソフトとは、インターネットを通じて、どんな人でもファイル(音楽、映画、ゲーム、文書など)を送受信できるソフトウェアのことを指します。使用方法を間違えてしまうと、違法・開示請求の対象になってしまう可能性がありますので、十分に注意しましょう。
ここでは、torrent(トレント)の違法ケースや開示請求に関する様々な事柄についてご説明します。
トレント(torrent)で違法になるケース

ファイル共有ソフトの違法性は主に二つのケースで問われます。一つは、著作権で保護されているデータを違法にアップロードし、他のユーザーがダウンロード可能な状態にした場合です。
二つ目は、正規版が有料で提供されているコンテンツを、違法なアップロードが行われていることを認識しつつダウンロードした場合です。多くのユーザーが違法にファイルをダウンロードしているからと言って、その行為が許されるわけではありません。ファイルのアップロードやダウンロードが著作権を侵害しているかどうかが、違法性の判断基準となります。
違法となるファイルやコンテンツの例
- アニメ
- 映画
- ドラマ
- 音楽
- テレビ
- AV(アダルトビデオ)
トレント(torrent)で違法になるケースについて以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
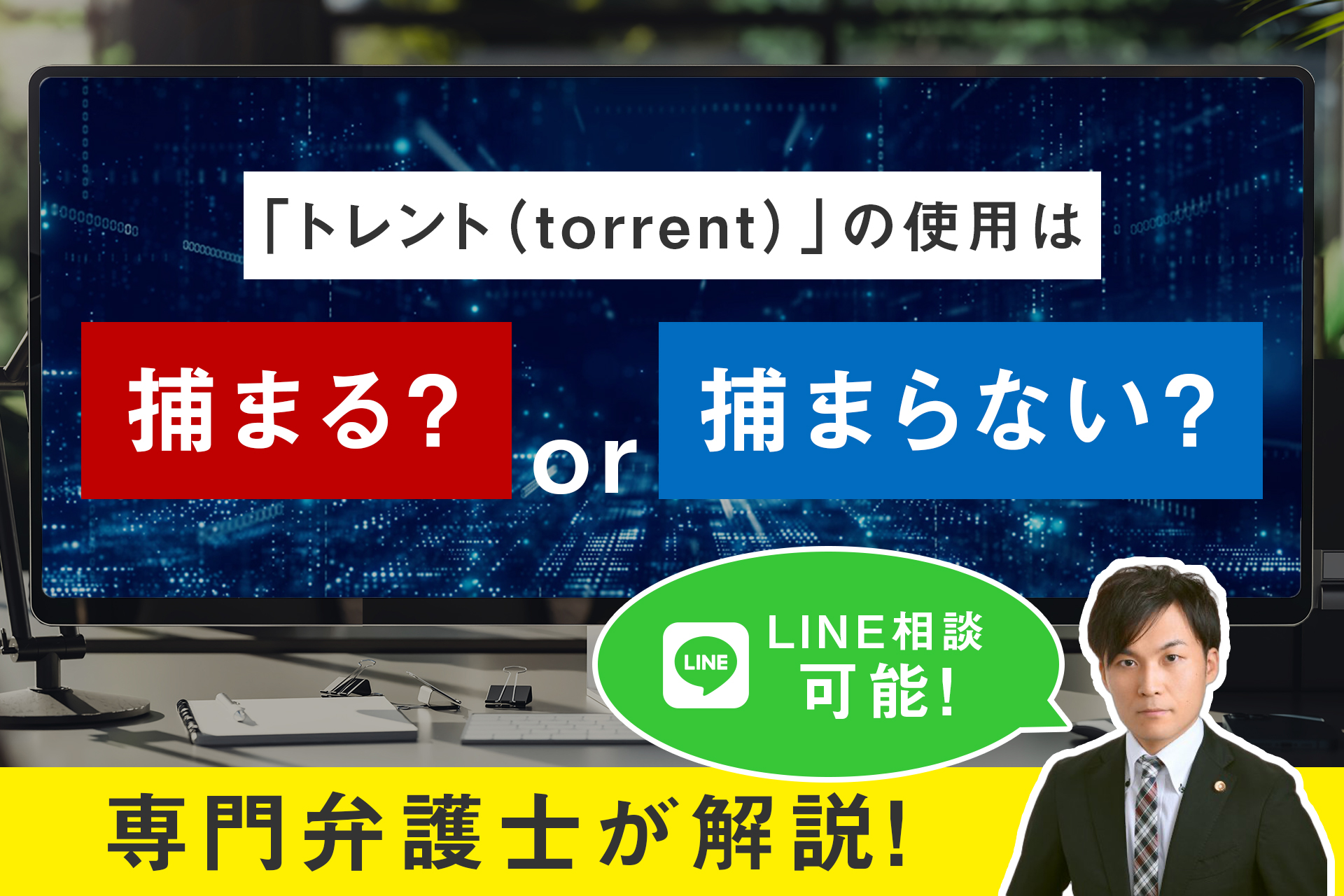
トレント(torrent)の違法がバレる仕組み

トレントはP2P技術を活用したファイル共有ソフトで、一般的なダウンロード手法と異なり、特定のサーバーに依存せず、ユーザー同士でデータを共有します。これにより、サーバーのダウンロード遅延やデータの消失などの問題が解消されます。ただし、トレントは原則としてダウンロードと同時に自分のデータを他のユーザーと共有することになっています。
つまり、ファイルのダウンロードと同時にアップロードも行われていることがほとんどです。
また、トレント自体は違法ではありませんが、著作権で保護されているコンテンツの違法ダウンロードやアップロードは罰せられます。インターネットには匿名性があり、問題のない通信であればそれを行ったユーザーの個人情報の特定は困難です。しかし、違法行為が行われた場合、ISPは警察や裁判所からの要請に応じてIPアドレスからの個人情報を開示します。
トレントの利用は個人情報の入力がないため匿名性が感じられますが、違法な行為があった場合には、ISPからの情報開示により身元特定が可能となるのです。
トレント(torrent)の違法がバレる仕組みについて以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
▶︎なぜトレント(torrent)で違法がバレる?IPアドレスの仕組みや特定について解説
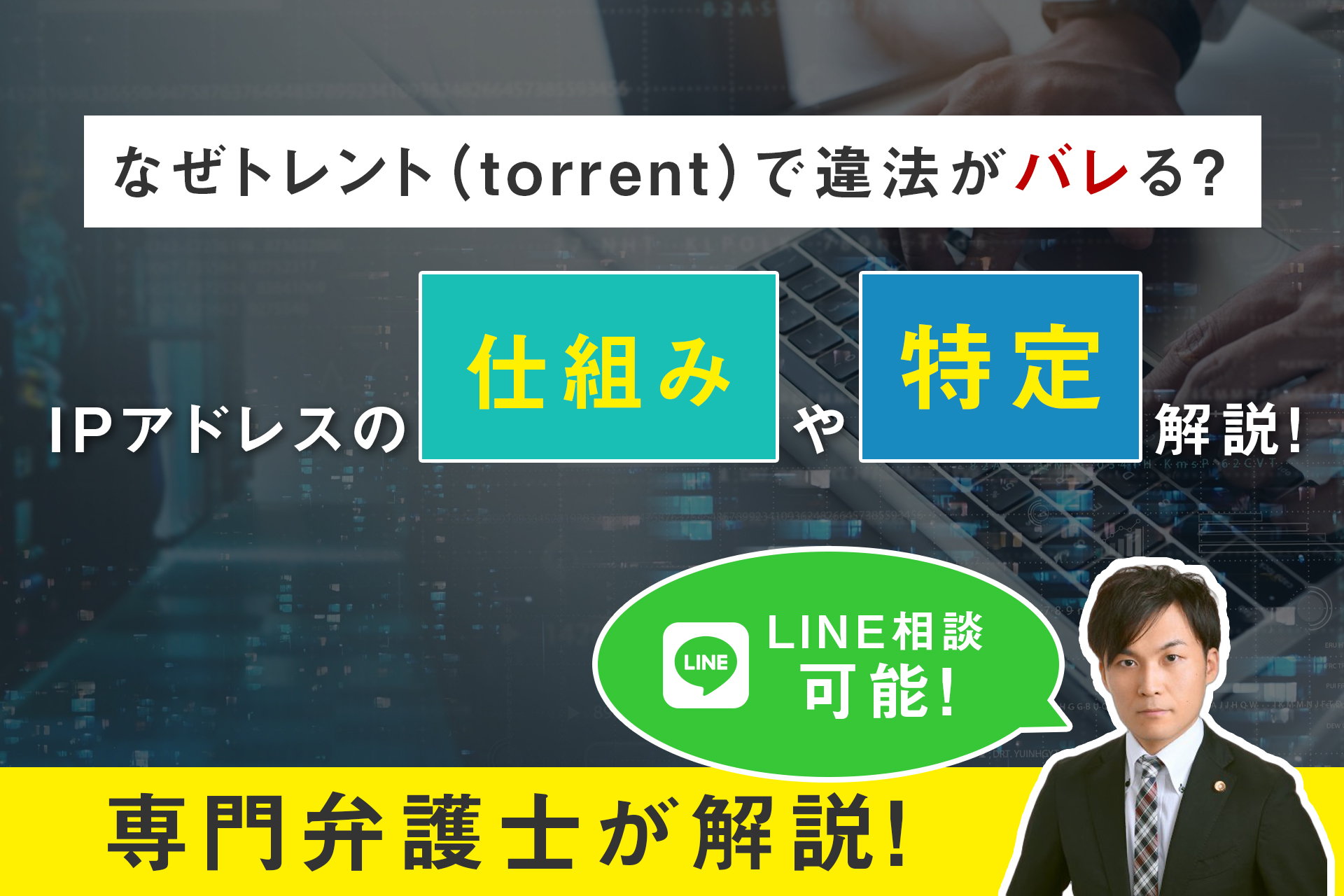
トレント(torrent)の違法で逮捕された事例

トレントの違法となるケースで過去に逮捕された事例としては、2010年にはテレビ番組を違法にアップロードしたユーザーが大きな損害賠償請求と共に逮捕されました。2019年と2021年にも、人気コミックやゲームソフト、アニメ等を違法にアップロードしたユーザーが逮捕されています。
実際に逮捕された後の処分や「トレント(torrent)」以外で過去に逮捕者が出たファイル共有ソフトについて、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
▶︎torrent(トレント)は逮捕される?されない?逮捕者の事例を解説
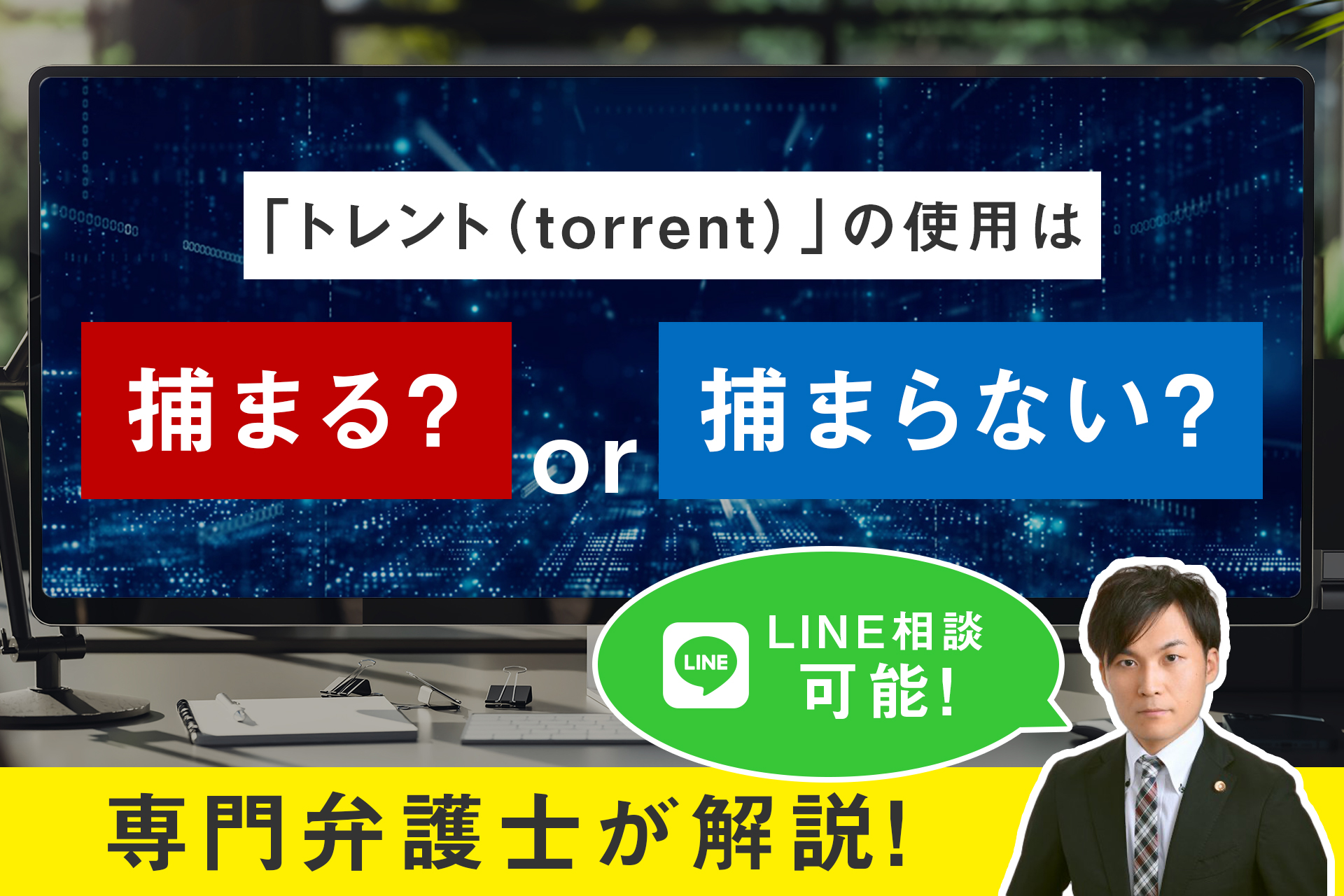
トレント(torrent)の違法に関する開示請求の示談金

「トレント」のようなファイル共有ソフトでは、違法にコンテンツをアップロードまたはダウンロードすると、著作権侵害となり刑事責任や民事責任(損害賠償責任)が生じる可能性があります。
被害を受けた著作権者は、「発信者情報開示請求」により加害者を特定することができます。これは、プロバイダに対し、加害者のIPアドレスなどの情報開示を求めるものです。
その後、被害者から加害者に対して損害賠償請求がなされます。発信者情報開示請求がなされた場合、必ずしも損害賠償の裁判に結びつくわけではなく、被害者と加害者が示談に応じる場合もあります。その際、通常、一作品あたり30〜70万円程度が示談金となりますが、違法にアップロードまたはダウンロードした作品の数や種類により変動します。
トレント(torrent)の開示請求を受けた際の示談金について以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
▶︎トレント(torrent)の開示請求受けたら示談金を払うの?相場や過去事例を弁護士が解説!

まとめ
torrent(トレント)のようなファイル共有ソフトを使用する際は、細心の注意を払いながら、正しい使用方法を心がけることが大切です。
もし、故意や過失などを含めたtorrent(トレント)からの開示請求が来た時は、まずは当事務所へご相談ください。



